|
認定特定非営利活動法人ラオスのこども
|
団体ID |
1051713277
|
法人の種類 |
認定特定非営利活動法人
|
団体名(法人名称) |
ラオスのこども
|
団体名ふりがな |
らおすのこども
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
「ラオスのこども」は1982年に活動を始めました。
ラオスのこども 略年表 1982年 「ASPBラオスの子どもに絵本を送る会」として日本語の絵本や学用品をラオスに寄贈する ことから活動を始める 1990年 ラオス語図書を初めて出版する 1991年 ラオス事務所を開く 1992年 一般・古典図書、創作作品の出版を始める 移動図書箱運動を始める 1993年 日本の絵本にラオス語を貼付して送る活動を始める 東京事務所を開く 1994年 子ども文化センターを設立する 1995年 紙芝居制作セミナーの普及活動を始める 学校図書室(ハクアーン)の開設を始める 1998年 ラオスの紙芝居を日本で出版する 2002年 外務大臣表彰を受ける 法人格の取得にともない、「特定非営利活動法人ラオスのこども」に名称を変更 2003年 民話絵本コンクールと紙芝居コンクールを行う 2005年 ビエンチャン都子ども教育開発センターの設立を支援する 受賞歴について 団体 •2002年 7月 外務大臣表彰 •2006年 5月 ラオス政府情報文化省大臣感謝状 •2008年 国際児童図書評議会(IBBY)「朝日国際児童図書普及賞」 •2016年 7月 社会貢献者表彰 個人 代表理事 チャンタソン インタヴォン •1992年 7月 日本青年会議所主催 TOYP大賞'92 外務大臣賞 •1999年 9月 毎日新聞社「毎日国際交流賞」 受賞 •2000年12月 アジア人権基金「アジア女性・人権特別賞」受賞 •2018年 JICA理事長賞 •2020年 旭日双光章 |
代表者役職 |
代表理事
|
代表者氏名 |
チャンタソン インタヴォン
|
代表者氏名ふりがな |
ちゃんたそん いんたぼん
|
代表者兼職 |
ホアイホン職業訓練センター代表
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
143-0025
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
大田区
|
|
市区町村ふりがな |
おおたく
|
|
詳細住所 |
南馬込6-29-12,303
|
|
詳細住所ふりがな |
みなみまごめ
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
alctk@deknoylao.net
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-3755-1603
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
03-3755-1603
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
住所 |
Noui 4, Ban Saphangmo, Muang Saysettha, Vientiane, Lao P.D.R. P.O.Box 1518
|
郵便番号 |
111-111
|
|
国名 |
Lao P.D.R
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
||
ボランティア |
||
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1980年1月1日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2003年5月8日
|
|
活動地域 |
海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
海外
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
25名
|
|
所轄官庁 |
東京都
|
|
所轄官庁局課名 |
東京都
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
子ども、青少年、在日外国人・留学生、教育・学習支援、地域・まちづくり、文化・芸術の振興、人権・平和、国際協力、国際交流
|
|
設立以来の主な活動実績 |
1982年から日本とラオスで活動を続けている国際協力NGOです。教科書、教材などが整わず、小学校を卒業できない子どもたちが今なお多いラオスで、絵本出版、学校図書室開設を行うとともに、「子どもセンター」では活動をきっかけに感性を豊かに伸ばし、子どもたちが可能性を大きく広げていくことをめざしています。また国内では地域、学校、企業のみなさんに向けて、活動の報告、ラオスの食、織物などの文化を紹介するイベントなどを開催しています。
これまでに、ラオス語図書194種類約84万冊を出版、ラオスの小中高校のうち2732校に図書セットを配付、246校で学校図書室を開設支援を行いました。 |
|
団体の目的
|
子どもが自らの力を伸ばす権利、人生を主体的に選択する権利を全うできるよう、教育の普及に協力することで、公正で平和な地球社会づくりに貢献することです。そのため、今日子どもが教育を受ける機会を十分得ていない地域のひとつ、ラオスにおいて、本の出版、読書の習慣の普及、子どもが集い遊び学べる場の支援など、子ども自らが学ぶ力を伸ばす環境を生み出す活動を行います。活動を通じて得た知識、情報は地域と地球社会に発信していきます。活動にあたっては、子どもの参加と、日本およびラオスをはじめとした人々の参加を促し、誰もが対等に力を発揮し合う関係を作り出すことで、それぞれが成長の機会を得ることをめざします。
|
|
団体の活動・業務
|
●図書出版プロジェクト・・絵本、民話、絵とき辞書などの子ども向けの図書をはじめとした、ラオ ス人作家によるラオス語の作品や海外作品の翻訳を現地で出版しています。
●読書推進プロジェクト・・読書を通して子どもたちの世界を大きく広げるため、ラオス国立図書館 の「読書推進運動」に協力し、全国の子どもたちに本を届けています。 また、継続的に読書に親しむことができるよう、空き教室に本棚などの備品と本を整備し、運営方 法や読書のすすめ方などを伝え、学校に図書室を作ります。 ●子どもセンター・・工作、音楽、踊りなど学校ではおこなわれていない表現活動の場として、セン ターの運営を支援しています。 ●人材育成・・こうしたプロジェクトが、将来は現地の人々によって担われるよう、先生に対してセ ミナーなどを開催しています。 |
|
現在特に力を入れていること |
●図書出版プロジェクト・・絵本、民話、絵とき辞書などの子ども向けの図書をはじめとした、ラオ ス人作家によるラオス語の作品や海外作品の翻訳を現地で出版しています。
●読書推進プロジェクト・・読書を通して子どもたちの世界を大きく広げるため、ラオス国立図書館 の「読書推進運動」に協力し、全国の子どもたちに本を届けています。 また、継続的に読書に親しむことができるよう、空き教室に本棚などの備品と本を整備し、運営方 法や読書のすすめ方などを伝え、学校に図書室を作ります。 ●子どもセンター・・工作、音楽、踊りなど学校ではおこなわれていない表現活動の場として、セン ターの運営を支援しています。 ●人材育成・・こうしたプロジェクトが、将来は現地の人々によって担われるよう、先生に対してセ ミナーなどを開催しています。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
ラオスにおける読書推進活動で、担い手のひとりひとりの思いを繋ぎ、ネットワークを形成し、子どもたちの教育環境を改善する活動が、自立していくことを大きなテーマとしています。
さらに2つの基本方針として、1.ラオスの急激な社会変化の中でNGOの役割を再確認する 2.羅王事務所の自立を促進する ことをあげ、4つの重点項目として、1.組織活動の質を高める 2.健全な財務体質を構築する 3.東京・ラオスともに活動の担い手の主体性・専門性を高める 4.プロジェクト評価とプロジェクトの方向性の再構築を図る と設定しています。 |
|
定期刊行物 |
・ラオスのこども通信 年に3回 1500部
「ラオスのこども通信」は、定期的に発行している会報誌です。活動内容や出版物紹介、ラオスの教育事情などを分かりやすく伝えています。 バックナンバーは以下をご覧ください。 http://homepage2.nifty.com/aspbtokyo/part_5/part_5.htm |
|
団体の備考 |
なし
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
JICA草の根技術協力事業、日本NGO連携無償資金協力事業、公益財団法人ベルマーク教育助成財団、
大同生命国際文化基金、今井記念海外協力基金、大田区助成金、庭野平和財団、日本国際協力財団などその他多数実績あり |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
他のNPOや大田区の市民活動団体と「ラオス語絵本づくりプロジェクト」という当会独自のボランティアプログラムを協働で開催、実施。
「ラオス語絵本プロジェクト」とは、日本の絵本にラオス語の翻訳シートをはり、ラオス語の本にする誰でも参加できるボランティア活動である。出来上がった絵本は、私たちが支援しているラオスの学校へ届けられる。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
企業や、学校で、毎年数回「ラオス語絵本づくりプロジェクト」という当会独自のボランティアプログラムを協働で開催、実施している。
「ラオス語絵本プロジェクト」とは、日本の絵本にラオス語の翻訳シートをはり、ラオス語の本にする誰でも参加できるボランティア活動である。出来上がった絵本は、私たちが支援しているラオスの学校へ届けられる。 |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
なし
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
7月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
総会
理事会 |
会員種別/会費/数 |
•活動会員:継続的に活動および運営を担ってくださる方(総会で議決権があります)
年度会費:一般 6,000円(2014年10月より改訂) 学生 3,000円 ※会員期間 入会年7月~翌年6月 •サポーター(賛助会員):活動に深く関われないが、活動を応援してくださる方(総会での議決権はありません) 年度会費:1口 5,000円以上 ※会員期間 入会月から1年 会員の特典(活動会員、サポーター会員共通) ・勉強会、イベント、スタディーツアーなどに会員割引料金あり ・年3回、ニュースレター「ラオスのこども通信」の送付 ・会員向けメーリングリストへの登録 会員数:160名 |
加盟団体 |
JANIC, JNNE
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
0名
|
12名
|
| 非常勤 |
0名
|
0名
|
|
| 無給 | 常勤 |
1名
|
0名
|
| 非常勤 |
12名
|
0名
|
|
| 常勤職員数 |
12名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
25名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
30名
|
||
報告者氏名 |
野口 朝夫
|
報告者役職 |
事務局長
|
法人番号(法人マイナンバー) |
5010805001286
|
認定有無 |
認定あり
|
認定年月日 |
2020年1月29日
|
認定満了日 |
2024年11月25日
|
認定要件 |
相対値基準
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















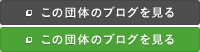
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する