|
特定非営利活動法人農都会議
|
団体ID |
1178442644
|
法人の種類 |
特定非営利活動法人
|
団体名(法人名称) |
農都会議
|
団体名ふりがな |
のうとかいぎ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
NPO農都会議は、市民協働と地域協働の理念のもとに、勉強会・フィールドワーク等を通じて、市民、地域からの政策提言とその実現をめざしています。現在、バイオマスアカデミー、バイオマスWG、農都交流・地域支援G、食・農・環境Gの四つのグループがあります。
|
代表者役職 |
代表理事
|
代表者氏名 |
山本 登
|
代表者氏名ふりがな |
やまもと のぼる
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
158-0091
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
世田谷区
|
|
市区町村ふりがな |
みなとく
|
|
詳細住所 |
中町2-40-13
|
|
詳細住所ふりがな |
はままつちょう
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
info@nouto-kaigi.org
|
|
電話番号
|
電話番号 |
090-7634-4602
|
連絡先区分 |
自宅・携帯電話
|
|
連絡可能時間 |
18時00分~22時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
-
|
連絡先区分 |
-
|
|
連絡可能時間 |
-
|
|
連絡可能曜日 |
-
|
|
備考 |
-
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
2010年1月29日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2016年4月28日
|
|
活動地域 |
全国
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
100万円~500万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
13名
|
|
所轄官庁 |
東京都
|
|
所轄官庁局課名 |
生活文化局 都民生活部 管理法人課
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
環境・エコロジー
|
|
|
地域・まちづくり、経済活動の活性化、市民活動団体の支援、農山漁村・中山間、食・産業、漁業、林業、行政への改策提言
|
|
設立以来の主な活動実績 |
2010年1月、政策提言全国ネットワークの「農都地域部会」発足。
2013年4月、FIT(固定価格買取制度)施行など東日本大震災後のエネルギー政策を取り巻く環境変化を受け、農都地域部会内に再生可能エネルギーと木質バイオマス発電・熱供給に取り組む「バイオマスWG(ワーキンググループ)」と、食の安全等に取り組む「食・農・環境G(グループ)」を設置。 2016年4月、農都地域部会を「NPO法人農都会議」へ組織変更。農山漁村・都市交流と地域のバイオマス資源による事業化を支援する「農都交流・地域支援G」を設置。 2019年4月、CO2削減効果の大きい熱利用の普及をめざす「バイオマスアカデミー」を設置。 2020年7月、書籍『実務で使うバイオマス熱利用の理論と実践』を発刊。 2022年12月、冊子『地域の脱炭素化シリーズ勉強会報告』を発刊。 |
|
団体の目的
|
本会は、市民協働と地域協働の理念のもとに,わが国の農山漁村及び中山間地域の振興を図る事業,バイオマスなど再生可能エネルギーの普及事業,温暖化防止や生物多様性などの自然環境を保全する事業,環境教育事業等を行い,また,地域におけるソーシャルビジネスの開発・普及・人材育成事業等の育成を行う。これらを通じて,本法人は,地域経済の発展と環境保全が両立する社会の実現を図り,もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
|
|
団体の活動・業務
|
本会の目的を達成するため次の事業を行います。
(1) 広報・宣伝事業 (2) 再生可能エネルギー普及事業 (3) 環境保全・環境教育事業 (4) 研修・体験・交流事業 (5) コンサルタント事業 (6) その他、目的達成のため各種の活動 |
|
現在特に力を入れていること |
農都会議は、地球環境保全と持続可能な循環型社会をめざし、「市民協働」、「地域協働」を基本理念に、自然資本を生かしながら脱炭素と循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けた活動を進めてまいります。市民・企業・地域の現場の課題を、勉強会やフィールドワーク等を通じて提言に取りまとめ、その実現をフォローしていきます。
活動を続けるために、自主的に運営する事業型NPO として新たな一歩を踏み出しています。各グループ等の連携による地域エネルギーサービス会社づくりで地域のエネルギー自給を応援していきます。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
農都会議は、一人ひとりが伸び伸び活躍できる社会づくりを進めたいと思っています。提言や事業化支援などの活動を継続するため、趣旨に賛同していただける個人の皆さま、法人・団体の皆さまは、入会して活動を支えてくださいますようお願いいたします。
農都会議へ入会していただくと、会員ニュースの配信や無料イベント参加、定例勉強会の参加費半額、会員限定の交流会参加、地域の再エネ・熱利用事業化の個別相談などさまざまな特典があります。再エネ・バイオマス・農林業等について情報・意見交換するメーリングリストへご参加いただけます。 |
|
定期刊行物 |
会員ニュース(月2回発行のメールマガジン)
|
|
団体の備考 |
現在、運営委員20名、会員 約200名(バイオマスWG含む)。ML参加者 約1000名(二つのMLの合計)
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
2020年度、緑と水の森林ファンド助成事業
|
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
1. 2020年1月14日に、ちば里山・バイオマス協議会、飯能木質バイオマスエネルギー協議会、いばらき里山・バイオマス協議会と4団体協働で「台風災害から考える気候変動」勉強会を開催。
2. その他にも諸団体と連携し、再生可能エネルギー、森林・林業、地方創生等のテーマでシンポジウム等を開催。https://blog.canpan.info/noutochiiki/img/WGandNoutokaigi-archives.pdf 3. 2019年7月16日に、JORA、ガス協、JWBA、BIN、シュタットベルケ、JSC-Aと7団体協働で「 地域型バイオマス推進に向けた基本的考え方」提言を発表し、併せて「地域型バイオマスフォーラム」を開催しました。 4. その後、環境省と地域型バイオマスに関する意見交換を定期的に行っています。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
1. バイオマスボイラーのメーカー、設計・施工業者、コンサルタント会社、研究者等と協働して、書籍「実務で使うバイオマス熱利用の理論と実践」を2020年7月に発刊。
2. 東邦大学理学部と共同で「地域における木質バイオマス熱利用に関する人材育成及び木質バイオマスボイラー導入の普及に関する研究」を実施。2022年2月に「共同研究成果発表シンポジウム」を実施。 |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
実績なし
|
最新決算総額 |
100万円~500万円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
971,340円
|
|
|
| 寄付金 |
10,000円
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
207,000円
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
12,014円
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
1,200,354円
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
847,664円
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
1,334,366円
|
|
|
| 内人件費 |
410,073円
|
|
|
| 次期繰越金 |
713,652円
|
|
|
| 備考 |
令和5年度は、昨年度までに続いて新型コロナウイルス感染症が継続する中、本法人の「市民協働」と「地域協働」の理念の下、再生可能エネルギー導入の普及及び地域のバイオマスエネルギー事業化支援の活動に絞って、勉強会のオンライン等による開催、提言、地域協議会へのサポート等の非営利活動を実施した。そのため、環境保全・環境教育事業及び研修・体験・交流事業の実施は見合わせた。今後は、コロナ五類移行等の状況変化に対応して、活動の継続を期していきたい。
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
1,630,843円
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
1,630,843円
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
917,191円
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
917,191円
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
713,652円
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
971,340円
|
|
|
| 受取寄附金 |
10,000円
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
207,000円
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
12,014円
|
|
|
|
| 経常収益計 |
1,200,354円
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
924,293円
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
410,073円
|
|
|
|
| 経常費用計 |
1,334,366円
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
847,664円
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
713,652円
|
|
|
|
| 備考 |
令和5年度は、昨年度までに続いて新型コロナウイルス感染症が継続する中、本法人の「市民協働」と「地域協働」の理念の下、再生可能エネルギー導入の普及及び地域のバイオマスエネルギー事業化支援の活動に絞って、勉強会のオンライン等による開催、提言、地域協議会へのサポート等の非営利活動を実施した。そのため、環境保全・環境教育事業及び研修・体験・交流事業の実施は見合わせた。今後は、コロナ五類移行等の状況変化に対応して、活動の継続を期していきたい。
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
1,630,843円
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
1,630,843円
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
917,191円
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
917,191円
|
|
|
| 正味財産合計 |
713,652円
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
713,652円
|
|
|
意志決定機構 |
理事会
|
会員種別/会費/数 |
個人正会員/年会費1万円/
法人・団体正会員/年会費5万円/ 個人賛助会員/年会費5千円/ 法人・団体賛助会員/年会費3万円/ |
加盟団体 |
気候変動イニシアティブ
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 無給 | 常勤 |
3名
|
|
| 非常勤 |
10名
|
3名
|
|
| 常勤職員数 |
|
||
| 役員数・職員数合計 |
13名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
7名
|
||
報告者氏名 |
杉浦 英世
|
報告者役職 |
代表理事
|
法人番号(法人マイナンバー) |
5340005004453
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
2021年度
|
|||
|
2020年度
|
|||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
2021年度
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















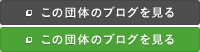
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する

