|
公益社団法人日本精神保健福祉士協会
|
団体ID |
1241377827
|
法人の種類 |
公益社団法人
|
団体名(法人名称) |
日本精神保健福祉士協会
|
団体名ふりがな |
こうえきしゃだんほうじんにほんせいしんほけんふくししきょうかい
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
精神保健分野のソーシャルワーカーである精神保健福祉士(国家資格)を正会員とする公益社団法人
|
代表者役職 |
会長
|
代表者氏名 |
田村 綾子
|
代表者氏名ふりがな |
たむら あやこ
|
代表者兼職 |
大学教授
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
160-0015
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
新宿区
|
|
市区町村ふりがな |
しんじゅくく
|
|
詳細住所 |
大京町23-3 四谷オーキッドビル7階
|
|
詳細住所ふりがな |
だいきょうちょうにじゅうさんのさん よつやおーきっどびるななかい
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
office@jamhsw.or.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-5366-3152
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時30分~17時30分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
03-5366-2993
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時30分~17時30分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1964年11月19日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2004年6月1日
|
|
活動地域 |
日本全国および海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
43名
|
|
所轄官庁 |
内閣府
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
子ども、青少年、障がい者、高齢者、福祉、保健・医療、災害救援、人権・平和、国際交流、就労支援・労働問題、行政への改策提言、学術研究(複合領域分野、その他)
|
|
設立以来の主な活動実績 |
<設立経緯>
本協会は、1964年11月に精神科ソーシャルワーカー(Psychiatric Social Worker:PSW)の全国組織「日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会」として発足し、1997年の「精神保健福祉士法」成立を契機に「日本精神保健福祉士協会」に名称を変更、2004年6月に社団法人となり、2013年4月に公益社団法人に移行しました。 構成員は12,246人(2023年3月11日現在)になっており、構成員を都道府県単位で区分した内部機関となる都道府県支部があります。 <沿革> 1964年 日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会設立(会員数88人) 1965年 「PSW通信」、機関誌「精神医学ソーシャル・ワーク」創刊 1982年 協会宣言採択「精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動をすすめる」ことを協会の基本方針とする。 1988年 「倫理綱領」を制定 1997年 「精神保健福祉士法」制定 1999年 「日本精神保健福祉士協会」へ名称変更 2004年 「社団法人日本精神保健福祉士協会」設立許可(6月1日付) 2011年 第8回通常総会において「公益社団法人への移行」を決議 2013年 「公益社団法人日本精神保健福祉士協会」へ移行(4月1日付) 2014年 設立50周年(11月19日) 2016年 代議員制施行(4月1日付) 2018年 「公益社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領」から「精神保健福祉士の倫理綱領」に名称変更 2020年 第8回定時総会において英語による表記及び略称を「Japanese Association of Mental Health Social Workers」及び「JAMHSW」に変更(6月21日付) 2022年 毎年6月を「社会的復権を語ろう月間」と定める 2024年 設立60周年(11月19日) |
|
団体の目的
|
精神保健福祉士の資質の向上を図るとともに、精神保健福祉士に関する普及啓発等の事業を行い、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めることにより、国民の精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
|
|
団体の活動・業務
|
1)事業一覧
<公益目的事業> 精神障害者等の生活と権利の擁護、精神保健福祉士の職務に関する知識及び技術並びに倫理及び資質の向上、資格制度の充実発展並びに普及啓発、精神保健福祉及び精神保健福祉士の調査研究、国内外の関係団体との連携を通じて精神障害者等の支援を図る事業 <収益事業> 精神保健福祉士養成及び精神保健福祉の普及啓発、精神保健福祉士賠償責任保険の普及に関する事業 2)事業項目 (1)精神障害者等の精神保健福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護に関すること。 (2)精神保健福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。 (3)精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。 (4)精神保健福祉士の資格制度の充実発展並びに普及啓発に関すること。 (5)精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査研究に関すること。 (6)災害時における精神保健福祉の援助を必要とする人々の支援に関すること。 (7)国内国外の社会福祉専門職団体やその他の関係団体との連携に関すること。 (8)その他目的達成のために必要なこと。 ※上記事業は、日本全国及び国外において行うものとする。 |
|
現在特に力を入れていること |
<2024年度重点課題>
1.人材育成 中期計画の中間年において着実に計画の遂行を図りつつ、法改正、報酬改定などに対応した研修内容の提供を進めていく。中でも、昨年度スタートした新たな認定精神保健福祉士の更新制度の浸透を図り、より充実した生涯研修制度の土台を強固にする取り組みを推進する。これらの研修事業による精神保健福祉士の資質向上はもとより、次世代育成に更に力を入れる。精神保健福祉士資格取得者および構成員の増加に向け、養成機関などと協働する連携教育の取り組みや構成員マイページ上の「私の研鑽データ」活用を促進し、e ラーニング教材の提供なども含め、魅力ある研鑽システムの構築を推進する。 2.政策提言 2024年度からの各種法改正施行後の現場での運用やそれに伴う実践を踏まえ、さらなる提言に必要な根拠を得るための実態把握、調査研究等を行う。そこで得た知見を行政府、立法府など各所に伝え、必要に応じて意見書や要望書を提出する。また、精神保健医療福祉の関係諸団体との協働や協議による適切な意見表明を行う。さらなる提言に必要な根拠を得るための実態把握、調査研究等を行い、各所へ意見書や要望書を提出することに加え、行政府、立法府等をはじめとする、精神保健医療福祉の関係諸団体との協働や協議による適切な意見表明を行う。 3.組織強化 中期計画の中間年度となる本年度では、計画達成のために従前からの委員会体制を大きく再編し、連関する委員会同士の結びつきを深め、相乗効果を高めることを目指す。また、将来ビジョンに掲げた9つの実践の具現化に向けてマクロ領域を俯瞰しながら、理事会がより一層本分に集中できる体制作りに着手し、専門的・社会的活動を全国展開するための盤石な組織体制の確立を目指す。 以上を踏まえ、定款第3条に掲げる「精神保健福祉士の資質の向上を図るとともに、精神保健福祉士に関する普及啓発等の事業を行い、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進めることにより、国民の精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする」を達成するため、定款第4条に基づく各種事業に取り組むこととする。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 中期計画(2026)【計画年度:2022~2026年度】(概要版)
人材育成、組織強化、政策提言それぞれの3つの柱として、ミクロ 主体性の尊重、メゾ 多様性の尊重、マクロ 包摂性の追求を定め、それぞれに重点的な取り組みをしめしている。 なお、重点的な取り組みの各項目の最後に示す委員会等は、主に担当する内部組織名を指す。 【人材育成】 <ミクロ 主体性の尊重の重点的な取り組み> ・ 自己決定の原理と意思決定支援について学ぶ機会の提供(研修企画運営委員会) ・ 専門職として主体的に「自己教育」できる人材の育成(構成員の「さくらセット」利用率50%)(認定制度推進委員会) ・ 将来ビジョンについて、すべての構成員の理解と実践の促進(都道府県支部、全国大会、機関誌、事務局等) <メゾ 多様性の尊重の重点的な取り組み> ・ 多様性の尊重について学ぶ機会の提供(研修企画運営委員会) ・ 各ブロックで認定SVRによるGSVを実施(認定SVR養成委員会) ・ ブロック等における養成校と都道府県協会等との連携教育の推進(都道府県支部、ブロック会議、理事会) <マクロ 包摂性の追求の重点的な取り組み> ・ 共生社会実現に向けたソーシャルアクションに取り組む人材の育成(研修企画運営委員会、課題別研修、全国大会等) ・ 新認定精神保健福祉士制度の定着(認定制度推進委員会) ・ eラーニング制度の構築(研修企画運営委員会、事務局) 【組織強化】 <ミクロ 主体性の尊重の重点的な取り組み> ・ 現業精神保健福祉士6割の入会(1.5万人)(組織強化委員会) ・ 全国組織としての組織体制の在り方の検討(組織強化委員会) ・ 業務指針の活用促進(都道府県支部) ・ 倫理綱領改訂の検討(「精神保健福祉士の倫理綱領」改訂検討委員会) <メゾ 多様性の尊重の重点的な取り組み> ・ 代議員制度の構成員への浸透と代議員機能の有効化の促進(組織強化委員会) ・ メディア機能の理解を深め、有益な活用の推進(メディア連携委員会) ・ 都道府県支部・ブロック単位での災害支援体制、減災意識に対する普及啓発(災害支援・復興支援委員会) <マクロ 包摂性の追求の重点的な取り組み> ・ 精神保健福祉士の資格取得者増加策の強化(理事会、事務局) ・ 構成員が情報や意見交換のできるプラットフォーム環境を検討(事務局) ・ 全国組織としての当事者、家族、他団体等との関係の発展、協働の推進(理事会) 【政策提言】 <ミクロ 主体性の尊重の重点的な取り組み> ・ エビデンスに基づいた各制度・政策等の改定・改正への要望書等の提出(理事会、委員長・リーダー) ・ 関係省庁、関係団体とのつながりの強化(理事会、事務局等) ・ 自殺予防対策、子ども家庭支援、依存症対策、貧困、災害支援等に対する適切な支援につながる仕組み作り(理事会、委員会・分野別プロジェクト) <メゾ 多様性の尊重の重点的な取り組み> ・ 非自発的入院の在り方の是正・改正に向けた調査研究(権利擁護部) ・ 都道府県支部・ブロック活動における好事例の情報収集・発信、関係組織や地域への啓発の実施(理事会、ブロック会議) ・ 全世代に対する福祉教育の導入(理事会等) <マクロ 包摂性の追求の重点的な取り組み> ・ 精神保健福祉士のあるべき姿に向けた養成カリキュラムに関する調査研究(特別委員会) ・ 精神科医療における人員配置基準を一般医療に近づける提言(理事会、権利擁護部) ・ 精神障害者の社会的復権の実現に向けた精神保健福祉法改正への提言(理事会、委員会) |
|
定期刊行物 |
・機関誌「精神保健福祉」(年4回発行)
・構成員誌「Members' Magazine『精神保健福祉士』」(年6回発行) |
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
2020~2024年度:厚生労働省/自殺防止対策事業「こころの健康相談統一ダイヤル」相談体制支援事業
2024年度:厚生労働省/令和6年度障害者総合福祉推進事業「退院促進措置における退院後生活環境相談員による支援の質の向上に資する研修に関する研究」 2023年度:厚生労働省/令和5年度障害者総合福祉推進事業「改正精神保健福祉法施行後の退院促進措置の有効な実施に関する運用ガイド等の作成」 2023年度:厚生労働省/令和5年度依存症民間団体支援事業「依存症にかかわる福祉人材の基盤づくりのための福祉系大学生等を対象とした『アディクション・オープンゼミナール2023』」 2021~2024年度:厚生労働省/こころの健康づくり対策事業「心のケア相談研修」事業を実施 2017年度:厚生労働省/医療観察法対象者における障害福祉サービスの活用状況の実態把握と受け入れを促進させるための方策に関する研究 2017年度:大阪府/平成29年度自殺対策強化事業 2015~2017年度:社会福祉振興・試験センター/アジア太平洋地域における児童家庭問題・災害対応等のソーシャルワーク実践に関するシンポジウム及びワークショップ開催・国際交流事業 2011~2017年度:社会福祉振興・試験センター/精神保健福祉士人材養成・研修事業 2010~2017年度:社会福祉振興・試験センター/精神保健福祉士リーダー研修事業 2016年度:厚生労働省/指定一般相談支援事業所(地域相談支援)と精神科病院の職員が協働して地域移行に向けた支援を行なうための研修カリキュラム及びガイドライン等の開発事業 2015年度:厚生労働省/精神障害の特性に応じたサービス提供ができる従事者を養成するための研修プログラム及びテキストの開発事業 2014年度:日本財団/精神科ソーシャルワーカーから精神保健福祉士への変遷と組織活動に関する史料の作成事業 2014年度:日本社会福祉弘済会/ソーシャルワーク研修2014 2011~2013年度:厚生労働省/精神保健福祉士実習指導者講習会事業 2011年度:厚生労働省/精神症状等を有する認知症患者に係る退院支援パス等の地域連携の推進に関する調査事業 2011年度:大和証券福祉財団/東日本大震災被災地支援に係る災害時ボランティア活動 2011年度:損保ジャパン記念財団/東日本大震災被災地支援に係る精神保健福祉士派遣事業 2011年度:ジャパン・プラットホーム/東日本大震災被災地支援に係る精神保健福祉士派遣事業 2011年度:社会福祉専門職団体協議会/東日本大震災被災地支援活動事業 2011年度:ソーシャルワーク教育団体連絡協議会/東日本大震災被災地支援活動事業 2010年度:福祉医療機構/みんなで考える 精神障害と権利 2009年度:社会福祉事業研究開発基金/こころのユニバーサルデザインハンドブック 精神障害のある人への生活支援と「障害者の権利条約」 2009年度:日本財団/社団法人日本精神保健福祉士協会災害支援ガイドライン 2009年度:厚生労働省/心神喪失者等医療観察制度における地域処遇体制基盤構築に関する調査研究事業報告書 2009年度:厚生労働省/精神保健福祉士養成カリキュラム改正に伴う実習指導者及び実習担当教員養成研修のプログラム開発事業報告書 2008年度:厚生労働省/精神障害者地域移行支援特別対策事業~地域体制整備コーディネーター養成研修テキスト~ 2007年度:厚生労働省/良質な相談支援を支える地域のしくみ作りに関する人材育成研修プログラム開発 2007年度:厚生労働省/精神障害者の地域移行支援~事例調査報告からみる取り組みのポイント~ 2006年度:厚生労働省/精神障害者の退院促進支援事業の手引き 2006年度:厚生労働省/精神障害者退院促進支援事業の効果及び有効なシステム、ツール等に関する調査研究」報告書 2005年度:みずほ福祉助成財団/精神保健福祉士教育養成課程における実習の指標に関する調査研究」報告書 |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
<加盟・連携・役員就任>
○(認定NPO)日本障害者協議会:正会員・理事就任 ○(一社)日本発達障害ネットワーク:正会員・代議員・理事就任 ○(公財)日本障害者リハビリテーション協会:評議員就任 ○(公社)日本精神保健福祉連盟:正会員・理事就任 ○精神保健従事者団体懇談会:会員及び代表幹事就任 ○国民医療推進協議会:構成団体及び理事就任 ○チーム医療推進協議会:正会員 ○日本ソーシャルワーカー連盟:構成団体 ○ソーシャルケアサービス従事者研究協議会:構成団体 ○救急認定ソーシャルワーカー認定機構:理事就任 ○(一社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟:理事就任 ○アルコール健康障害対策基本法推進ネットワーク:幹事団体 ○(公財)日本精神衛生会:理事 ○(一財)社会福祉研究所:評議員 <役員等派遣> ○ソーシャルケアサービス従事者研究協議会:ソーシャルワーク・ケアワークの専門性の評価に関する研究 ○(NPO)地域精神保健福祉機構:リカバリー推進フォーラム企画 ○(公社)日本社会福祉士会:地域における成年後見制度の利用に関する相談体制やネットワーク構築等の体制整備に関する調査研究事業/地域共生社会の実現に資する体制構築を推進するソーシャルワークのあり方に関する実証的調査研究事業 ○(公財)日本財団:就労支援フォーラムNIPPON ○(一社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟:地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士の養成のあり方及び人材活用のあり方に関する調査研究事業 ○(公社)日本医療社会福祉協会:災害福祉支援活動研修実施事業 ○日本神経精神薬理学会:「統合失調症薬物治療ガイドライン」改訂 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
<厚生労働省>
2016年度~2018年度:障害者政策総合研究事業「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」/分担研究「地域における多職種連携によるケアマネジメントに関する研究」及び分担研究「措置入院患者の地域包括支援のあり方に関する研究」 2017年度:精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究事業/分担研究「新しい精神保健指定医研修・審査のあり方に関する研究」 <文部科学省> いじめ対策防止協議会 委員 <法務省> “社会を明るくする運動”中央推進委員会 構成団体 <消費者庁> 高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会 構成団体 <東京都> 2008~2011年度:被保護者退院促進支援事業 2011年度:医療観察法地域処遇体制基盤構築事業 <中野区> 2007~2009年度:精神保健福祉支援プログラム <国立精神・神経センター(現・国立精神・神経医療研究センター)> 2009年度:精神保健と社会的取組の相談窓口の連携のための調査委託事業 <福岡県> 2006年:精神障害者社会復帰促進研究事業 |
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
総会/一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)上の社員総会
・代議員(法人法上の社員)をもって構成する。 ・代議員数は、概ね構成員150人当たり1人の割合とし、構成員(正会員及び準会員)の中から、都道府県毎の構成員数に応じた割合の代議員を代議員選挙によって選出する。 ・代議員数は84人(2025年3月現在) |
会員種別/会費/数 |
次の4種とし、正会員及び準会員を「構成員」(12,396人/2025年3月現在)という。
(1)正会員 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けた者及び大学等で精神保健福祉士の養成及び研究に従事する者であって、本協会の目的に賛同して入会した者。 (2)準会員 本協会設立以前から、精神科病院その他の施設において精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う業務に従事する者であって、理事会が別に定める基準によって入会した者。 (3)賛助会員(個人8人、企業等5団体/2017年3月現在) 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。 (4)名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者。 |
加盟団体 |
国際ソーシャルワーカー連盟、日本ソーシャルワーカー連盟、公益社団法人日本精神保健福祉連盟、ソーシャルケアサービス従事者研究協議会、特定非営利活動法人日本障害者協議会、精神保健従事者団体懇談会
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
1名
|
10名
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
22名
|
|
|
| 常勤職員数 |
|
||
| 役員数・職員数合計 |
43名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
|
||
報告者氏名 |
|
報告者役職 |
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















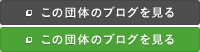
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する