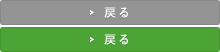事業成果物名 |
2024年度ナノ流体を用いた排ガスCO2回収技術の開発(2年目)
|
||||||||
団体名 |
|||||||||
事業成果物概要 |
1. プロジェクト概要
[課題] エネルギー関連設備を運営する事業主に於いて、燃焼後のCO2回収技術はアミンスクラビングが主流ですが、エネルギー消費量が多いことが課題です。 経済的でエネルギー効率の高いCO2回収プロセスは、地球温暖化を緩和するために化石エネルギー源からのCO2排出を抑制するための必須条件となっています。 [期待される成果・効果] ·ナノ流体の検討・評価:ナノエマルション、マイクロエマルション、ナノ粒子、アミン系界面活性剤または共界面活性剤を検討・評価。 ·溶媒とナノ流体の再生温度と熱負荷の低減を比較し、回収/脱着プロセスの全体コスト、競争力のある吸脱着性能と再生エネルギーを検討。 ·再生可能エネルギーの供給予測検討と風力・太陽光発電から発生する水素と回収したCO2を用いるメタネーションプロセス安定化。 ·リスク管理機能技術開発とデジタルツイン・モデルのチューニングに関する技術開発。 ·外部の専門調査企業に委託し、市場分析を行います。 2. 2年目の事業成果 <WLPGA GTC2023でカーボンフットプリント削減賞を受賞した本化学技術の精度向上> ·液-液(ナノエマルジョン)および固-液(ナノ粒子分散液)の安定系をCO2吸着剤として作成し、試験することに成功しました。 ·ナノエマルションを生成する界面活性剤、油分、添加剤のバランスを調査し、ナノ粒子を10nmにする配合を確認。このナノエマルションは、ナノ粒子分散液よりもCO2吸収剤として優れた性能を示す事を確認しました。 ·この結果はナノ粒子の液滴サイズが小さいことにより、液体‐気体界面積が高いことと、使用されるアミン系界面活性剤が界面のアミン官能基の濃度を高めた結果と推測されます。 ·ナノエマルジョン、ナノ粒子分散液、両方でナノ粒子への影響調査を実施し、3回のCO2吸収/脱離繰返しでも影響がないことを確認しました。 ·CO2吸収液(ナノ流体)に関する技術動向および効果的な特許出願戦略(特許出願権利化策)を策定することを目的に知財調査を実施しました。 複数のアミンを混合した複合アミン吸収液が多く確認されましたが、ナノエマルジョンCO2吸収液として、ノニオン系界面活性剤とアミン系界面活性剤の配合比率と粒子径(ナノエマルジョン)との関係を規定することが出来れば新規性を有するとの結果が出たため、特許出願は可能と判断できました。 <多種のアミンに対応可能な動的モデル構築技術の開発検討> ·吸着塔/再生塔プロセスモデルの検討アミン吸着塔のモデルを作成し、多種のアミンに対応可能な動的モデル構築技術となるアミン吸収の物性のチューニング機能を開発し、実証を実施しました。 ·デジタルツイン・モデルを利用し、実プラントでは確認できないプラント内部の可視化を表示できるように3D可視化技術の研究を開始し、FSを実施しました。 <再生エネルギー発電モデル開発検討> ·緯度・経度情報、時刻情報および日射変化を設定することで太陽光発電量を推算するモデルを開発しました。 ·10分平均の風況予測データをWeibull分布に基づいた高頻度風況データ(1秒程度)に変換する機能を含む風力発電量が推算できるモデルを開発しました この2つの再生エネルギー発電モデルにより、不安定な再生エネルギー発電の動的シミュレーションが可能となり、水電解装置によるH2生成ならびにメタネーションプロセスの最適運転の評価が可能となりました。 3.今後は、以下の項目を継続して実施していく予定です。 ·リスク管理機能技術開発(動的なハザード推定・検証機能) [事業:ID2024013912/海底パイプライン輸送における水素・天然ガス混合物の監視技術の開発(3年目)]で開発中のリスク管理機能技術のリスクアセスメントにはHigh Fidelityなデジタルツインのモデルが必要であるため、今後は実データを用いたデジタルツイン・モデルのチューニングに関する技術開発・検証を継続して行う予定です。 リスクアセスメント手法の一つのHAZOP手法を利用し、リスク要因によるプラントへの影響(最終事象)をデジタルツイン上で再現し、安全対策までも検証までできるシステムを開発開始しています。 ·ナノ流体の調査とその結果のシミュレーションへの組込みを継続して続け、特許出願するためのデータ収集を継続実施します。 ·ナノエマルジョンの継続使用による安定性の調査と吸収CO2単位当たりのエネルギコストの調査を実施します。 ·再生エネルギー電力網の動的シミュレーションの再現性の精度向上を図るため、実データとの比較および評価を継続的に実施します。 |
||||||||
助成機関 |
|||||||||
事業成果物種類 |
報告書
|
||||||||
事業成果物 |
|