|
西東京にほんご教室(任意団体)
|
団体ID |
1018185718
|
法人の種類 |
任意団体
|
団体名(法人名称) |
西東京にほんご教室
|
団体名ふりがな |
にしとうきょうにほんごきょうしつ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
|
代表者役職 |
代表
|
代表者氏名 |
山辺 真理子
|
代表者氏名ふりがな |
やまべ まりこ
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
-
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
-
|
|
市区町村ふりがな |
-
|
|
詳細住所 |
-
|
|
詳細住所ふりがな |
-
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
nishitokyo.nihongo.class@gmail.com
|
|
電話番号
|
電話番号 |
-
|
連絡先区分 |
-
|
|
連絡可能時間 |
-
|
|
連絡可能曜日 |
-
|
|
備考 |
-
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
|
連絡先区分 |
|
|
連絡可能時間 |
|
|
連絡可能曜日 |
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
|
|
ボランティア |
|
|
関連ページ |
|
|
閲覧書類 |
|
|
設立年月日 |
1995年4月1日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
|
|
活動地域 |
市区町村内
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
100万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
0名
|
|
所轄官庁 |
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
在日外国人・留学生、国際交流
|
|
設立以来の主な活動実績 |
1995年4月:国内に定住外国人が増加し、全国に日本語ボランティア教室ができるのと時期を同じくして、旧保谷市で市内唯一の日本語ボランティア教室として活動をスタートした。
2002年:2001年に保谷市が田無市と合併、西東京市になったことを受けて「保谷にほんご教室」から「西東京にほんご教室」に改称した。市内のボランティア団体に呼び掛け、日本語ボランティア連絡会を立ち上げ「西東京市日本語ボランティア教室案内」を作成し、市内公共団体窓口に設置、情報の周知を図った。活動紹介のパネル展示なども行った。 2008年6月:設立時からの活動拠点だった住吉公民館の閉鎖に伴い、新たにオープンした保谷駅ビル・ステア内の「保谷駅前公民館」に拠点を移し、現在に至る。 活動が20年以上に及ぶことから、親子二代、親戚などの参加、また、以前の学習者がボランティアになるなど活動の継続が外国籍住民の地域参加や参画につながってきている。一方、日本人の地域参加の受け皿にもなっており、地域に引っ越してきた人や子育て後、または退職後の地域参加者を受け入れ、外国籍住民とともに住みやすい地域づくりに一役買っている。 外部団体への協力として、毎年春と夏の長期休暇にボランティアセンターの依頼で、体験ボランティアを受け入れている。市内の小学校の国際理解教育にも多文化共生センターと協力して、外国籍住民と共に参加している。 現在の代表者は設立以来のメンバーで三代目になる。ボランティア活動は個々人の思いや時間を持ち寄りフラットな関係の上にあるという信念の元、活動のまとめ役、行政等との連絡窓口を担っている。 |
|
団体の目的
|
西東京市及び周辺地域に在住する日本語を母語としない人、多様な文化的背景を持つ人の、地域での生活がより快適なものとなるようサポートし、同じ地域住民として、交流し学び合う。
|
|
団体の活動・業務
|
西東京にほんご教室は、年末年始・祝日を除く毎週土曜日、午後2時より4時まで保谷駅前公民館の会議室で日本語を母語としない人に日本語学習支援をしており、現在のボランティアスタッフは約20名、学習者は変動があるものの常時10名前後が参加している。
学習者の希望に応じて、マンツーマンで日本語能力テストの勉強、日本人とあまり話す機会がないという人たちはグループでの会話、家庭の事情などで日本に来たばかりの中学生などは日本語の学習や学校の勉強などを教師経験のあるスタッフがみている。 学習だけではなく、ティータイムの時間を設け、各国のお土産を食べたり、新しく参加した学習者の自己紹介の時間になっている。 文化交流という面でも毎年4月には近くの公園でお花見、年末にはパーティを開き、その折には各国の家庭料理などを持ち寄り、作り方を教えあったりすることもある。茶道をたしなむ日本人スタッフが中心になって、毎年催されるお茶会は日本文化にふれる場として、特に女性にはとても人気がある。 また、最近では日本語の学習のあと、英語で自分の国の紹介や文化などを自由に話す時間を作り、まだ日本語があまり上手でない学習者も参加している。 地域の情報を提供する場として、加入している「NPO法人西東京市多文化共生センター」から得る多言語版の市の広報誌などの配布やまた日本人スタッフから地域の情報など(ゴミの捨て方やスーパーの情報)を得る貴重な場にもなっている。震災、計画停電などの情報もメールで流し、少しでも不安の軽減になるようつとめた。 業務としては、代表・総務・会計をおき、年1回の総会の開催や、公民館等活動場所の確保、市内の他の教室との連絡など会の運営をおこなっている。 2011年にスタートし、毎週更新しているCANPANブログにより、会の運営がよりオープンでスムーズなものになってきている。 |
|
現在特に力を入れていること |
活動25年目に入ったが、誰でも、いつからでも参加できる場を開いていることが会のモットーで、常に最優先事項である。ほとんど日本語が分からない人から、日本語には困らないが日本社会に溶け込めない人の居場所として、より広い世界への入り口でありたいと願っている。日本人等スタッフも世代やバックグラウンドも様々だが、各自が自分の意見を言いやすい雰囲気づくりも大切にしている。
設立当初は外国人女性配偶者と日本語学校生、大学生が多かったが、ここ数年多様な参加者に出会い、時代の変化を感じる。例えば小さな子ども連れの男性の配偶者、日本に在住する子どもたちを訪ねての短期滞在の老夫婦、国際結婚家族の子どもたち、再婚での呼び寄せ家族等である。最近は中国からのIT技術者も多くなっていたが、リーマンショック以後帰国する人も増えた。地域の日本語教室は世界のニュースが身近に感じられる場所でもある。 そういう中で、多様な参加者がアクセスしやすい環境と、発信しやすい環境を作りたいと考え、2011年度よりITを使ってその環境を整えていく時期と位置付け、会のブログを作り、日本人も外国人も発信できるようにし、会としての発信も複数の人が担える体制作りを行っている。 ボランティア活動は、小規模ならではのフットワークの軽さがある半面、参加メンバーの合意形成が大切で、そこには時間を掛けつつ、状況の変化に柔軟に対応していきたい。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
|
|
定期刊行物 |
|
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
|
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
|
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
|
最新決算総額 |
100万円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
|
会員種別/会費/数 |
|
加盟団体 |
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 常勤職員数 |
|
||
| 役員数・職員数合計 |
0名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
|
||
報告者氏名 |
|
報告者役職 |
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















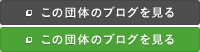
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する