|
認定特定非営利活動法人エッジ
|
団体ID |
1113879132
|
法人の種類 |
認定特定非営利活動法人
|
団体名(法人名称) |
エッジ
|
団体名ふりがな |
えっじ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
NPO法人エッジはディスレクシアの正しい認識の普及と支援を目的とした特定非営利活動法人として、2001年10月に認定設立され活動しています。ディスレクシアは知的に問題が無く、聴覚・視覚の知覚的機能は正常なのに、読み書きに関しては特長の有るつまずきや学習の困難を示す症状のことを言います。ディスレクシアの全ての人が活き活きと暮らせる社会を目指します。 一人の人間の一生にかけての問題ですから、広く研究者、行政、教育機関、メディアなど多方面に働きかけ、ディスレクシアの全ての人が活き活きと暮らせる社会にするために広く啓発活動を行い、ディスレクシアの人たちの支援をして、関係する人たちのネットワークを作ります。
1) 啓発活動:イベントなどの開催をする。メディアへ情報を提供する。 2) 支援:相談窓口を開設し、情報の提供をする。 3) ネットワーク作り:専門家、支援者のネットワーク作りの核をまず東京で作り、その後各地への展開をするディスレクシアに関する情報センターの役割を担う。 |
代表者役職 |
会長
|
代表者氏名 |
藤堂 栄子
|
代表者氏名ふりがな |
とうどう えいこ
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
108-0014
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
港区
|
|
市区町村ふりがな |
みなとく
|
|
詳細住所 |
芝4-7-1 西山ビル4階
|
|
詳細住所ふりがな |
とうきょうとみなとくしば にしやまびる
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
edgewebinfo@npo-edge.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-6809-4465
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
|
|
閲覧書類 |
|
|
設立年月日 |
2001年10月19日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2001年10月19日
|
|
活動地域 |
日本全国および海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
12名
|
|
所轄官庁 |
東京都
|
|
所轄官庁局課名 |
生活文化局都民生活部地域活動推進課
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
子ども、青少年、障がい者、福祉、保健・医療、就労支援・労働問題
|
|
設立以来の主な活動実績 |
エッジは2001年に設立以来発達障害のなかのLD(学習障害)の中核症状であるディスレクシア(読み書きの困難)がある人たちが本来の力を発揮して活き活きと暮らせる社会を目指している。啓発、支援とネットワークを3本の柱として、当事者性を第一にして、先駆的、独自性を常に念頭に置き全人的な対応ができるよう活動している。
25年間で4つの法案の立案、施行にかかわってきた。現在でもそれぞれの法律の検討委員や審議委員となり法律の施行を見守っている。 発達障害者支援法 教科書バリアフリー法 障害者差別解消法 読書バリアフリー法 また関連して政策提言、具体的なプログラム構築、実施をしてきている 当初はディスレクシアへの支援について先進国である諸外国を視察した。①イギリス、フィンランド北欧、アメリカ、シンガポール、香港など。 2016年から2021年ASEAN諸国10か国訪問、交流し多様な言語、文字、文化、宗教、民族を包摂する「アジア・太平洋ディスレクシアフォーラム」を5回にわたって主催した」③) 「見方を変えて味方を増やす」 ホームページ、メルマガ、SNSを通じて発信をするとともに、当事者による講座やコンサルテーションを行っている。 適切な支援や指導ができる人材を育成している。特別支援教育支援員をはじめとする養成講座(2006年から港区のローカルライセンス②①、各地で地域のNPO等とつながり講座の実施を拡充①、コロナでオンライン、e-ラーニング)、読み書き困難指導支援講座(ロンドン大学のコルセラを和訳①、日本語のコースを展開①、英語のコースを構築)、アセッサー養成講座(e-ラーニング)①④。多くの支援者を輩出してきている。 当事者の読み書きの困難さを評価して適切な支援につながるために、保護者の相談、本人のアセスメントができるようプログラムを構築した。④ 広く安価に現場で役立てる集団アセスメントを展開中である。①⑤ 「多様な学びに応える」 音声教材(平成20年から調査研究、BEAMを制作提供、光文書院の単元テストの音声化、他の団体へ音声提供)①⑧ 読書バリアフリー法に準じて各地の図書館、学校図書館にて視覚障害ではない、読み書きの困難さのある人たちの情報保障をするべく活動をしている。 「EDGEを活かす」 読み書きの文字を音に変えてスラスラと正確に読み、観たものや考えていることをすらすらと正確に手書きすることだけが困難であれば技術を使ったり、読み書きの補完をしたり、様々なカタチで情報保障をすることで本来の力を発揮することが可能であることを当事者たちのことばで伝えてきている。啓発、NEXT EDGEエンパワメントセンター構想に着手 得意を活かす:アートコンペ(2023年から)、K&Tクラブ(居場所、仲間に出会う:メタエッジ⑦)、DX会(2005年から)NODE(2023年から)。 ① 日本財団、GB笹川、スカンジナビア笹川、 ② 港区助成金 ③ 国際交流基金 ④ 子ども輝く東京・応援事業 ⑤ パブリックリソース ⑥ クラウドファンディング ⑦ こども家庭庁 ⑧ 文部科学省 |
|
団体の目的
|
ディスレクシア(読み書きの障害)とは広義の学習障害(LD-Learning Disabilities)
の中で、通常の知能を有しながら、特に読み、書きの能力に支障があるために教育の 現場での自己表現が困難な者をいう。この法人は、ディスレクシア本人と彼らに関わ る人々に対して、その症状の正しい認識と、診断または判断の後、学習における困難 さの分野と程度の認定、最も有効、ホリスティック且つ本質的な教育の指導方法・機 会・手段を提供しそれにより彼らに多くの可能性を与えられることを目的とする。 |
|
団体の活動・業務
|
■具体的には
(1) 啓発活動 ・ 社会の理解を得るための企業、学校、行政、PTA、民間教育機関、医療機関等に対するワークショップや講演を開催する ・ イベントなどの開催をする ・ メディアへ情報を提供する (2) ネットワーク作り ・ 専門家、支援者のネットワーク作りの核をまず東京で作り、その後各地への展開をする ・ ディスレクシアに関する情報センターの役割を担う (3) 支援活動 ・ 人材育成:ディスレクシアの支援ができる人材の育成 -LSA(学習支援員)の養成講座 基礎講座はe-learningで行っている ・ スクリーニング(支援方法を策定するためのチェックリスト)と教材を開発する ・ 相談窓口を開設する ・ 情報の提供をする |
|
現在特に力を入れていること |
1.学習支援員(LSA)養成の普及と充実
-2005年よりスタートし約250名を学習支援員養成しました。 -2008年に「能力を引き出し伸ばす支援」テキストを作成しました。 -2010年より各地に普及 -2014年よりe-learningを開始 -各地に展開(札幌、広島、大阪、宮崎) 2.ディスレクシアの成人の 就労支援活動 -2010年ディスレクシア成人の 就労ガイドブック作成 内容は 第1章 自分を知る 第2章 自分を知る2 第3章 自分を表現する 第4章 就職活動1 第5章 就職活動2 第6章 企業の見方 第7章 就職に関わる制度 -2010年 就労実績あり参加者全員 3.音声教材 BEAM の無償提供 現在小学校1年生から中学校3年生までの国語、社会が各2社分入手可 4.DX会とキッズ&ティーンズクラブの開催 本人のエンパイント、ジョリーフォニックス英語講座 5.DXセミナー(2014/10からほぼ毎月開講) 6.オンライン講座によるディスレクシアへの指導ができる教員及び支援者育成 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
NPO法人エッジはディスレクシアの人たちが生き生きと社会の中で暮らせるよう啓発、支援とネットワークの3つの柱を中心に活動をしています。
啓発) ディスレクシアとは読み書きの障害を指します。ディスレクシアであることは不便ですが必ずしも不幸ではありません。ただし特に教育と就労の場面で不利を被ることが多い人たちでもあります。 ☆ニュースレターを年3回発行して、活動報告をします。 ☆ホームページ ☆ラジオ、メルマガ、パンフレットを発行します。 ☆講座の講師も中高生、保護者、学習支援員、成人当事者など多岐にわたってディスレクシアの啓発にあたります。 ホームページ http://www.npo-edge.jp / メルマガ http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/cat_50004724.html ニュースレター http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/cat_50007440.html インターネットラジオ(DXステーション) http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/cat_50033715.html ディスレクシアセミナー http://blog.livedoor.jp/npo_edge/archives/cat_50051583.html 支援) ディスレクシアは治ることはありませんが、現在の先端機器やアナログな機器を使って十分に情報を得て、自分の考えていることを発信することもできます。また自分で工夫して、生き延びることができます。 ☆民間の学習支援員講座を星槎教育研究所と協同して開催しています。北海道・北見、川崎、葛飾、宮崎など全国各地で行います。 ☆東京都港区の公立小中学校へ協働事業(2006~2009年)、委託事業(2010~2013年度) として学習支援員を養成し、派遣しました。 ☆DX会(成人のディスレクシアの会)6回開催しています。ワークショップを中心に活動します。 ☆キッズ&ティーンズクラブ:小学生から高校生までのディスレクシアの生徒への講座を行います。 ☆教科書の音声化をしてクラウド上にアップし、どこからでもダウンロードでき、使用できるようにしました。BEAMと名付けました。 学習支援員(LSA) https://www.npo-edge.jp/support/lsa/ 音声教材(BEAM) https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/ ☆教員向けオンラインコースを構築中 ネットワーク) ☆ディスレクシア関係の支援団体(JDDネット、全国LD親の会など) ☆学会(LD学会、日本ディスレクシア研究会など) ☆海外ディスレクシアの団体(イギリスのADO、シンガポールのDASなど) ☆文部科学省、厚生労働省 ☆アジア太平洋の団体 |
|
定期刊行物 |
メルマガ(月一回)
http://www.npo-edge.jp/educate/mailmag/ ニュースレター(年三回) http://www.npo-edge.jp/educate/newsletter/ |
|
団体の備考 |
2008年・第39回博報賞「特別支援教育部門」受賞
テーマ「NPOと自治体の協働による特別支援教育の推進」 JDDNET発足団体 |
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
●日本財団 「学習支援員制度の普及」
●福祉医療機構 「成人ディスレクシアのためのWSと就労マニュアル」「中小企業と発達障害の就労」 ●日英教育基金 「英国ディスレクシア視察」 ●フィランソロピー協会 IT機器、ウェブサイト構築 ●アサヒワンビールクラブ 「飲み物」 ●カルピス 「飲み物」 ●味の素 「賞品」 ●東京南ロータリークラブ 「子どものWS」「音声教材」 ●パルシステム 「LSA講座テキスト」 ●NHK厚生文化事業団 「PC3台」 ●グレイトブリテン・ササカワ財団 「英国視察旅行」 ●スカンディナビア・ニッポン・ササカワ財団 「スウェーデン視察旅行」 ●サントリー 「飲み物」 ●公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団「NPO基盤強化資金助成」 |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
●大学入試センター
2009年~2010年 「入試における合理的な配慮について」 ●日本リハビリテーション協会 2005年~2008年 「ディスレクシアに対するデジタル教材の在り方」開発、セミナー、モニターなど ●NPO34団体と 2002年~2006年 「港区NPOハウス運営」 ●星槎教育研究所 2010年~現在 「LSA養成講座」共催 ●カシオペア、リボンネット、チューリップ元気の会、フレンド 2009年~2010年 LSA制度の普及 ●東大先端研 2011年 ディスレクシアへのデジタル教材の提供 シンポジウム共同開催 ●ドコモ子ども未来財団 出版 ●ペガサス、オアシス福祉会、フラッグ 障害者就労支援 ●連合、中小企業同友会 障害者就労支援 ●他に、らんふぁんぷらざ、LD/ディスレクシアセンター、パルレ、東京都自閉症協会、えじそんクラブなどとシンポジウムなど共催多数 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
●IBM サービスモニター、シンポジウム、WS
●学研 アセスメント、啓発シンポジウム ●マイクロソフト モニター ●Tripod 製品モニター ●トーダン 物販 ●江夏画廊 WS、物販 ●アポーグループ 物販 ●イメージテン 映画作成 ●国際教育研究所 コンサート ●オリンパス 製品開発、障害者就労 ●黎明高校 インターンシップ、WS ●フジゼロックス 音声教材普及 ●キングジム 教材開発、WS |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
●文部科学省委託事業
2007年~2008年 「障害のある子供への対応におけるNPO等を活用した実践研究事業」 個別支援室と学習支援員の仕組みと効果 2009年~2011年 「障害のある子供への対応におけるNPO等を活用した実践研究事業」 音声教材の製作システムの構築と普及 2012年~2013年 「障害のある子供への対応におけるNPO等を活用した実践研究事業」 音声教材の普及 2014年 教科書課「音声教材作成の効率化」 ●港区教育委員会 2005年~2010年 学習支援員制度の構築と運営(協働) 2011年~2013年 学習支援員の配置(委託事業) |
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
1月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
313,000円
|
173,700円
|
80,000円
|
| 寄付金 |
7,621,209円
|
4,396,877円
|
8,120,000円
|
|
| 民間助成金 |
5,992,500円
|
6,019,000円
|
3,100,000円
|
|
| 公的補助金 |
1,450,000円
|
301,000円
|
400,000円
|
|
| 自主事業収入 |
7,846,104円
|
18,367,254円
|
17,350,000円
|
|
| 委託事業収入 |
7,073,656円
|
7,048,625円
|
8,380,000円
|
|
| その他収入 |
80,784円
|
60,444円
|
60,000円
|
|
| 当期収入合計 |
29,836,353円
|
36,366,900円
|
37,640,000円
|
|
| 前期繰越金 |
-15,230,848円
|
-13,755,672円
|
-13,755,672円
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)予算 |
| 当期支出合計 |
30,165,680円
|
34,492,397円
|
34,735,000円
|
| 内人件費 |
16,429,372円
|
2,950,393円
|
19,079,379円
|
| 次期繰越金 |
-15,630,175円
|
-13,755,672円
|
-11,881,169円
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
10,379,265円
|
8,852,581円
|
| 固定資産 |
10,000円
|
10,000円
|
|
| 資産の部合計 |
10,389,265円
|
8,862,581円
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
15,703,440円
|
14,570,253円
|
| 固定負債 |
10,316,000円
|
8,048,000円
|
|
| 負債の部合計 |
26,019,440円
|
22,618,253円
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
-15,230,848円
|
-15,630,175円
|
| 当期正味財産増減額 |
-399,327円
|
1,874,503円
|
|
| 当期正味財産合計 |
-15,630,175円
|
-13,755,672円
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
313,000円
|
173,700円
|
80,000円
|
| 受取寄附金 |
7,621,209円
|
4,396,877円
|
8,120,000円
|
|
| 受取民間助成金 |
5,992,500円
|
6,019,000円
|
3,100,000円
|
|
| 受取公的補助金 |
1,450,000円
|
301,000円
|
400,000円
|
|
| 自主事業収入 |
7,846,104円
|
18,367,254円
|
17,350,000円
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
7,073,656円
|
7,048,625円
|
8,380,000円
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
80,784円
|
60,444円
|
60,000円
|
|
| 経常収益計 |
29,836,353円
|
36,366,900円
|
37,640,000円
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
30,165,680円
|
34,492,397円
|
34,735,000円
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
-15,230,848円
|
-13,755,672円
|
-13,755,672円
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
-15,630,175円
|
-13,755,672円
|
-11,881,169円
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
10,379,265円
|
8,852,581円
|
| 固定資産合計 |
10,000円
|
10,000円
|
|
| 資産合計 |
10,389,265円
|
8,862,581円
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
15,703,440円
|
14,570,253円
|
| 固定負債合計 |
10,316,000円
|
8,048,000円
|
|
| 負債合計 |
26,019,440円
|
22,618,253円
|
|
| 正味財産合計 |
-15,630,175円
|
-13,755,672円
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
総会(年一回:2月)
|
会員種別/会費/数 |
正会員30人(年会費3000円∔寄付金)
賛助会員19人(年会費3000円) |
加盟団体 |
日本発達障害ネットワーク(JDDNET)
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
0名
|
1名
|
| 非常勤 |
0名
|
0名
|
|
| 無給 | 常勤 |
0名
|
0名
|
| 非常勤 |
0名
|
0名
|
|
| 常勤職員数 |
2名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
12名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
|
||
報告者氏名 |
藤堂 栄子
|
報告者役職 |
会長
|
法人番号(法人マイナンバー) |
8010405002938
|
認定有無 |
認定あり
|
認定年月日 |
2017年9月14日
|
認定満了日 |
2027年9月13日
|
認定要件 |
絶対値基準
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2025年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|||
|
2023年度(前々々年度)
|
|||
|
2022年度
|
|||
|
2021年度
|
|||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2026年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2025年度(前年度)
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|
|
2022年度
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















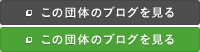
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する