|
一般財団法人日本蛇族学術研究所
|
団体ID |
1321190983
|
法人の種類 |
一般財団法人
|
団体名(法人名称) |
日本蛇族学術研究所
|
団体名ふりがな |
にほんへびぞくがくじゅつけんきゅうしょ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
ヘビ類の分類、生態学的研究をはじめ、その飼育、繁殖の研究を行っている。ジャパン・スネークセンターとしてヘビ類を中心にハ虫類を多く展示し、動物園としての役割も果たしている。
さらに蛇毒、毒蛇咬症、特にマムシ、ヤマカガシ咬症の病理学的の研究を行い、毒蛇咬症発生時の医療機関へのアドバイスを行うと同時に咬症のデータの収集を行っている。 また、学校や森林組合などの団体、医療機関などでの講演を行い、毒蛇の被害を減らすために、また適切な対処ができるように啓蒙活動を行っている。 |
代表者役職 |
理事長
|
代表者氏名 |
毬山 利一
|
代表者氏名ふりがな |
まりやま としかず
|
代表者兼職 |
株式会社陶陶酒本舗代表取締役社長
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
379-2301
|
都道府県 |
群馬県
|
|
市区町村 |
太田市
|
|
市区町村ふりがな |
おおたし
|
|
詳細住所 |
藪塚町3318
|
|
詳細住所ふりがな |
やぶづかちょう
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
snake-b@sunfield.ne.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
0277-78-5193
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 土 日
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
0277-78-5520
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 土 日
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
|
|
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1968年6月1日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
1968年6月1日
|
|
活動地域 |
日本全国および海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
群馬県
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
19名
|
|
所轄官庁 |
内閣府
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
観光、学術研究(理学)、学術研究(医学、歯学、薬学)
|
|
設立以来の主な活動実績 |
本研究所は、1968年、文部省所管の財団法人日本蛇族学術研究所が発足し、当初はヘビ類の医学的応用に関する研究を目的としていたが、その後、群馬大学の長谷川秀治学長、東京大学伝染病研究所の沢井芳男助教授等の尽力によってその趣旨を広げ、日本をはじめ世界各地のヘビ類の飼育、生態、分類、蛇毒および毒蛇咬症、蛇体成分の研究等を広く行うとともに、研究成果の発表、一般公開による啓蒙、および世界各国の関連する研究機関との交流ならびに情報・研究資料の交換等を行うことを目的として活動した。
当初より毎年奄美群島のハブ咬傷調査を行ってきた。1980年4月には沖縄県島尻郡玉城村に沖縄支所、1990年4月には毒蛇咬症国際研修センターを開設し、毒蛇咬傷調査、咬傷の予防、ハブ駆除対策を行ってきた。 また、ミャンマー、ネパール、イラン、中国など海外からの研修生を受け入れ、それぞれの国での抗毒素製造のために必要な毒蛇の飼育や採毒方法の研修を行った。さらに研究者の受け入れも行い、毒や抗毒素の共同研究も行った。 海外学術調査によりタイ、ミャンマー、フィリピン、インド、ネパール、スリランカ、中国などの毒蛇咬傷調査を行ってきた。 マムシ、ヤマカガシの毒作用と咬傷の病理学的研究を行い、国内では初めてヤマカガシ毒の作用、生体への作用を明らかにし、1984年の中学生の死亡例をきっかけに抗毒素を試作し、その後2000年に厚生科研費の研究班で新たに抗毒素を製造し、現在までに20例の重症例で抗毒素による治療により貢献した。 さらに一般や医療関係者からのヘビの判別や対処法、また、診断、治療などの問い合わせを電話とメールで年間500件ほど受けている。 併設のジャパンスネークセンターでは世界のヘビを展示すると同時に、ヘビについての啓蒙活動を行ってきた。マムシやヤマカガシ、家の周りで見られるヘビについての正しい知識を身につけてもらうための講演をセンター内だけでなく、小学校などに出向き行っている。さらに近年では違法に飼育されていた毒蛇や大蛇、屋外で捕獲されたペットのヘビ、トカゲ、カメなど毎年多くの個体を引き取っている。 |
|
団体の目的
|
当法人は、国内及び諸外国の蛇類やその咬症に関する研究を行うとともに展示飼育施設の運営を行い、成果の応用及び知識の普及等を図り、学術の振興と人と蛇類との共存に寄与することを目的とする。
|
|
団体の活動・業務
|
1.蛇類及び蛇毒の生化学的および薬理学的の研究。
2.毒蛇咬症に関する調査及び咬症の予防、診断、治療並びに病理学的研究。 3. 我国及び諸外国の蛇類の系統的な分類及び飼育、並びにその生理及び生態の研究。 4. 爬虫類研究に関する文献、記録等の情報資料の収集および世界各地の爬虫類研究機関等との交流。 5. 展示施設を運営し、国内外の蛇類の飼育展示及び爬虫類研究に関する各種資料等の展示公開。 6.蛇類及び毒蛇咬症等に関する情報の発信、社会教育活動。 7. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 |
|
現在特に力を入れていること |
毒蛇咬症の病理学的研究を行うと同時に、その成果を医療機関での講演及び当研究所でのマムシ対策研修講座を通じて、石や看護師、薬剤師などの医療関係者だけでなく一般の人にもヘビの判別や対処法、診断、治療などについての啓蒙活動を行っている。鹿児島県の委託による奄美群島のハブの生態研究では、東京大学医科学研究所と共同で行っている。また、警察や税関等からの依頼により、違法飼育のヘビ類の同定・保管・引き取りなどを行っている。社会教育事業では、大学や専門学校からの研修生の受け入れも積極的に行っている。「毒蛇110番」を開設し、一般からのヘビの判別や対処法、ペットに関する質問や咬傷発生時の医療機関等からの問い合わせに対応している。さらに、ヤマカガシ咬傷症発生時には診断と抗毒素の手配等も行っている。
|
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
|
|
定期刊行物 |
|
|
団体の備考 |
1.温室内における各種ヘビ類の飼育方法を確立した。
特に絶滅に瀕する恐れのあった天然記念物「岩国のシロヘビ」の人工繁殖に成功した。 2.毒蛇咬症の調査を行い、咬症の治療と予防の研究を行った。 特に、奄美・沖縄におけるハブ咬症の調査を行い、治療血清の精製、凍結乾燥、および治療方法を改良して重症患者の減少に寄与した。またヤマカガシ咬症の病因を研究し、治療血清を試作して重症患者の治療に成功した。 3.ヒメハブ毒より抗血栓剤であるトロンビン様酵素の分離精製に成功した。 4.マムシ類の分類の見直しを行った。 |
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
海外学術調査 文部省
アジアの毒蛇咬傷に関する国際会議 群馬県他 |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
実績無し
|
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
実績なし
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
奄美群島振興開発事業の1つとして鹿児島県からの委託事業として、「ハブとの共存に関わる総合調査事業」を東大医科学研究所奄美病害動物研究施設との共同で調査を毎年行っている。
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
理事会
|
会員種別/会費/数 |
会員制はとっていません
|
加盟団体 |
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
4名
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
9名
|
|
|
| 常勤職員数 |
3名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
19名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
2名
|
||
報告者氏名 |
毬山 利一
|
報告者役職 |
理事長
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
1968年6月1日
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
その他
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
公益財団法人会計基準
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















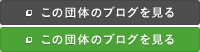
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する