|
公益財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構
|
団体ID |
1473124442
|
法人の種類 |
公益財団法人
|
団体名(法人名称) |
海と渚環境美化・油濁対策機構
|
団体名ふりがな |
こうえきざいだんほうじん うみとなぎさかんきょうびかゆだくたいさくきこう
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
当機構は、海洋環境保全を図ることにより漁場の回復と保全に努め、漁業経営の安定と国民の福祉の増進並びに水産業の振興に貢献することを目的に以下の3事業をおこなっております。
<漁場油濁被害対策事業> ・原因者不明の漁場油濁事故に対する被害救済及び防除清掃費用の支弁 ・原因者判明の漁場油濁事故であるが、原因者による措置が行われず被害漁業者が自ら清掃作業を実施した場合の費用の支弁 ・油流出事故対応に必要な基本的知識の講演や、海上でのオイルフェンス展張訓練他をおこなう油汚染防除指導者養成講習会の開催 ・油濁事故現場に専門家を派遣し現地調査及び漁業者等への指導 ・ホームページ等における、マニュアルやDVDの公開 等 <海と渚環境美化事業> ・海と渚の清掃活動を呼びかける「全国一斉海浜清掃旗揚げ式」の実施 ・周年を通じた、海浜清掃用ごみ袋の配布 ・「海浜等清掃活動実施状況調査」及び「漁民の森活動アンケート調査」 ・環境保全活動やその人材育成を目指す団体への助成金の交付 ・漁業系プラスチックごみ等の実態調査とバイオプラスチックを利用した使用済漁具のリサイクル 等 <漁業系廃棄物再利用支援事業> ・漁業者自らが圧縮減容機を利用した漁業系廃棄物の再利用支援 |
代表者役職 |
理事長
|
代表者氏名 |
坂本 雅信
|
代表者氏名ふりがな |
さかもと まさのぶ
|
代表者兼職 |
全国漁業協同組合連合会 代表理事会長
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
113-0034
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
文京区
|
|
市区町村ふりがな |
ぶんきょうく
|
|
詳細住所 |
湯島二丁目31番地24 湯島ベアービル7階
|
|
詳細住所ふりがな |
ゆしまにちょうめさんじゅういちばんちにじゅうよん ゆしまべあーびるななかい
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
info@umitonagisa.or.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-5800-0130
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
03-5800-0131
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
9時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
|
|
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1975年3月3日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2013年4月1日
|
|
活動地域 |
全国
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
17名
|
|
所轄官庁 |
内閣府
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
食・産業、漁業、林業
|
|
|
環境・エコロジー、助成活動
|
|
設立以来の主な活動実績 |
当機構は、1975年(昭和50年)3月に設立され、1977年(昭和52年)7月農林省、通商産業省、運輸省3省主務大臣の認可を受けた公益法人です。 2011年(平成23年)10月に (社)海と渚環境美化推進機構(1993年(平成5年)設立)を吸収合併して(財)海と渚環境美化・油濁対策機構となり、2013年(平成25年)内閣総理大臣の認定を受け、同年4月1日に公益財団法人へ移行いたしました。
当機構は、原因者不明の油濁事故に対する 防除清掃作業費の支弁を行う防除事業、被害漁業者に対する救済金の支給を行う救済事業を行うほか、油濁防止講習会を全国で開催し、油濁事故の際に防除事業を指導する専門家を派遣しています。 また、海と渚の環境美化のため海浜清掃の全国的な推進、普及及び海浜清掃活動の調査、漁民の森の活動調査、海の環境と漁業に関する調査並びに廃棄物の適切な処理推進、普及のための活動など海と渚の環境に関する普及・啓発及び調査活動を行っております。 |
|
団体の目的
|
海と渚の環境美化、水産資源の保護その他の海洋・海岸環境の保全整備を支援及び推進することにより、優れた自然環境を有する「青く豊かな海・美しい浜辺」の保全、保存、整備及び活用を図ること、並びに船舶、工場等から流出し、又は排出される油による漁場油濁であってその原因者が判明しないものについて、被害漁業者に対する救済金の支給を行うとともに、漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃を推進する措置を講ずることにより、被害漁業者の迅速な救済と漁場の保全を図り、もって国民の福祉の増進及び漁業経営の安定に資し、併せて水産業の振興に寄与することを目的としています。
|
|
団体の活動・業務
|
【事業】
当機構では、上記の目的を達成するため次の事業を行っております。 (1) 海と渚の環境美化、水産資源の保護その他の海洋・海岸環境の保全整備に関する活動の支援、推進及び普及・啓発 (2) 海と渚の環境美化、水産資源の保護その他の海洋・海岸環境の保全整備に関する調査研究並びに情報の収集、分析及び提供 (3) 原因者が判明しない漁場油濁による被害漁業者に対する救済金の支給 (4) (3)の漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃に要した費用の支弁 (5)原因者は判明しているが、原因者による防除措置及び清掃作業が行われない漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃に要した費用を支弁する事業並びに原因者による防除措置及び清掃作業は行われているが、漁場油濁の拡大の防止のため漁業者が行った防除措置及び清掃作業に要した費用の総額のうち、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第7条に定める船舶の所有者等の責任の限度額を超えた費用の支弁 (6) 漁場油濁の防止及び漁場油濁による被害の救済に関する調査、知識の啓発普及及び被害漁業者に対する指導 (7) 「海の羽根」募金運動の推進 (8) その他機構の目的を達成するために必要な事業 |
|
現在特に力を入れていること |
海の環境保全のため海を慈しみ、守り、後世に引き継いで行くことは、水に依存して地球に住む我々一人ひとりに課せられた大きな使命です。
この使命遂行を目的として、機構の実施する油濁被害救済対策は、原因者不明の油濁事故漁場汚染救済の国内唯一の制度として、1975年(昭和50年)の法人設立時から漁業者の皆様を守り続けてきました。油濁事故は水産物や漁具を汚染し、漁業者に甚大な損害を与えますが、特に原因者不明の事故の場合20パーセント超は原因者が不明であることから、漁業者が行う防除清掃に対し十分な経費負担の裏打ちがなされてきませんでした。これを改善するために行われているのが「漁場油濁被害防除清掃事業」です。 本制度は、国、都道府県、民間拠出団体の資金拠出で支えられており、設立から2017年度(平成29年度)まで、事業の対象となった事故は992件、支弁額は1,937百万円となります。そして、この事業には(公財)日本財団の助成を受けております。 また、当機構では、海と渚の環境を守るための清掃活動の全国的展開を推進するため、周年を通じてごみ袋の提供を行い、また、身近な海浜・河川などの環境美化の重要性を訴えるため都道府県等と協力し、海の日に「全国一斉海浜清掃旗揚げ式」を開催しております。 2017年度(平成29年度)には、(公財)日本財団の「海と日本プロジェクト 2017」と連携し、全国1,700ヵ所に自然物用ごみ袋32万枚、人工物用ごみ袋21万枚、合計54万枚を配布いたしました。なお、自然物用ごみ袋32万枚のうち、8万枚はJFマリンバンクからご提供をいただきました。 さらに、2017年(平成29年)8月26日には福岡県宗像市で、宗像国際環境会議実行委員会と共催、第37回全国豊かな海づくり大会実行委員会と連携し、第37回全国 豊かな海づくり大会~福岡大会~ のプレイベントとして、「全国一斉海浜清掃旗揚げ式」を開催し、全国津々浦々に向けて海浜等の清掃活動を呼びかけました。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
①漁業者を守る、原因者不明の油濁事故漁場汚染救済の国内唯一の制度としての「防除清掃事業」、「救済事業」の実施。
②漁場油濁事故の被害未然防止や被害を最小限に食い止めるための「油汚染防除指導者養成講習会」の精力的な開催 2017年度(平成29年度)からは、漁業関係者だけではなく民間企業・団体への講習会も開催いたしました。 ③事故被害を最小限に食い止めるため、流出油防除に不可欠なオイルフェンスに関する知識の一層の普及啓発 2018年度(平成30年度)、冊子「オイルフェンスとは・・・」を刊行。1997年(平成9年)のナホトカ号重油流出事故発生時、現場で実際に防除指揮をされた佐々木邦昭氏に執筆頂き、オイルフェンス使用に必要不可欠な基本知識を余すところなく公開し好評を得ております。 ④海浜清掃活動における民間の自主的活動を支援し、活動の機運の盛り上がりに一層貢献する、周年を通じたごみ袋の配布の強化 2015年度(平成27年度)以降、「海と日本プロジェクト」と連携することで、長年、要望のあった自然物用ごみ袋のサイズをひと回り大きく、更に、約10万枚/年 増刷で、ご要望を満たす数のごみ袋を配布が可能となり、より幅広く、漁協、NPO、ボランティア及び市民団体へのごみ袋の提供を行っております。 ⑤「海浜等清掃活動実施状況調査」及び「漁民の森活動アンケート調査」 当機構が、1997年度(平成9年度)から行っている「海浜等清掃活動実施状況調査」は、全国47都道府県及びごみ袋配布対象者から回答を得ており、日本国内の海浜清掃の経年変化を把握できる貴重な資料となっております。本資料は「海岸漂着物処理推進法」(平成21年法律第82号)の制定や、「海岸法」改正時の参考資料となっており、また「水産白書」や「海洋基本計画」の写真資料の出典となっております。 さらに「漁民の森活動アンケート調査」も2001年度(平成13年度)から40都道府県より回答を得ており、漁業者が行っている植樹活動の実態や、植樹活動の海洋環境、生物生産への関与の経年変化を把握できる貴重な資料であり「水産業・漁村の多面的機能」や「海は生きている」(富山和子著、2017講談社)のデータ等出典となっております。 ⑥漁業系プラスチックごみ等の実態調査とバイオプラスチックを利用した使用済漁具のリサイクルの推進 2018年度(平成30年度)からの新規事業として、実態調査では漁業や養殖業で利用されたプラスチック漁具や発泡スチロールを定量的に把握し、現場で適正に処理する計画を作成し、当該地域から発生源となる漁業系プラスチック廃棄物の海洋への流出を防止することを目的とし実施いたします。また、バイオプラスチックを利用した実証試験を実施し、将来の養殖業のプラスチック漁具の廃棄処理の簡便化、一層のコスト削減を図り、環境にやさしい漁業・養殖業の推進を図って参ります。 |
|
定期刊行物 |
「油濁情報」
発行頻度:年2回(夏号、冬号) 発行部数:2,800部 「メッセージ海と渚」 発行頻度:年2回(夏号、冬号) 発行部数:500部 |
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
2017年度(平成29年度)実績
<民間助成金> (公財)日本財団: 全国海浜清掃活動の推進(海でつながる)(海と日本2017) 8,204,000円 <国庫補助金> 農林水産省: 漁場油濁被害対策費補助金 19,695,000円 漁業系廃棄物対策促進事業費補助金 14,459,000円 <都道府県負担金> 39都道府県: 漁場油濁被害救済対策に要する費用 5,500,000円 (北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) <拠出団体拠出金> 民間拠出団体: 漁場油濁被害救済対策に要する費用 30,000,000円 ((公財)日本財団、(一社)日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、(一社)日本旅客船協会、石油連盟、電気事業連合会、(一社)日本鉄鋼連盟、(一社)日本経済団体連合会、(一社)日本電機工業会、(一社)日本自動車工業会、(一社)日本貿易会、(一社)日本産業機械工業会、石油化学工業協会、日本肥料アンモニア協会、日本化学繊維協会、(一社)日本セメント協会、(一社)日本ガス協会、(一社)大日本水産会) |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
特になし
|
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
特になし
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
特になし
|
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
理事会及び評議員会
|
会員種別/会費/数 |
会員種別:団体会員及び個人会員
会 費:団体会員1口1万円以上、個人会員1口5千円以上 会 員 数:団体会員192、個人会員10、合計202 |
加盟団体 |
―
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
1名
|
4名
|
| 非常勤 |
0名
|
1名
|
|
| 無給 | 常勤 |
0名
|
0名
|
| 非常勤 |
11名
|
0名
|
|
| 常勤職員数 |
4名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
17名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
0名
|
||
報告者氏名 |
|
報告者役職 |
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















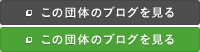
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する