|
特定非営利活動法人山の自然学クラブ
|
団体ID |
1561653815
|
法人の種類 |
特定非営利活動法人
|
団体名(法人名称) |
山の自然学クラブ
|
団体名ふりがな |
やまのしぜんがくくらぶ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
自然と肌で接することによって自然そのものをより深く理解し、その価値を学び、そこから学んだことを活かして、私たちに恩恵を与えてくれる自然に寄与する活動を行っています。
自然は長い時間をかけて今日の世界を作って来ました。大陸の移動、山の隆起、噴火や侵食、地質、その上に育った植物、そこにすむ動物、地球規模の気候変動による生物の移動。これらを知るにつけ、今の自然が我々に与えてくれる恩恵、価値に気づき、それを大切にしたいと思うのです。 様々な経験を持った会員が、自分の学んだことを活かして自主的に活動を行うことが私たちの基本姿勢です。ですから、いろんなことに取り組んでいる仲間が、それぞれ自由に活動をしています。 |
代表者役職 |
理事長
|
代表者氏名 |
大蔵 喜福
|
代表者氏名ふりがな |
おおくら よしとみ
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
160-0015
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
新宿区
|
|
市区町村ふりがな |
しんじゅくく
|
|
詳細住所 |
大京町25 高橋ビル402 緑化工ラボ内 担当:中村
|
|
詳細住所ふりがな |
だいきょうちょう
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
shizengaku@shizen.or.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-3341-3953
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~16時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
担当理事:中村
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
03-5362-7459
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~16時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金 土 日
|
|
備考 |
担当:中村
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1993年10月2日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2001年12月10日
|
|
活動地域 |
複数県
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
500万円~1,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
14名
|
|
所轄官庁 |
東京都
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
地域・まちづくり、環境・エコロジー、科学技術の振興、食・産業、漁業、林業、学術研究(理学)、学術研究(農学)
|
|
設立以来の主な活動実績 |
日本山岳会の自然保護委員会の中で、会員が山の自然を理解するために「山の自然学講座」を始めた。山の自然を学ぶ講義、シンポジウムなどを中心に活動を行ってきたが、それが発展し、学んで得た知識を実践する活動を本格的に行うため、2001年に特定非営利活動法人となる。当初メンバーは設立時の代表者(理事長)含め、日本山岳会の会員・自然保護委員が中心であった。
共に自然を学んでその価値を知り、自然保護の活動を行うことに関する事業を行い、好ましい地球環境の持続に寄与することを目的としている。 認証後、主な実践活動として、インタープリター、富士山南麓での植樹活動等をおこなっている。 |
|
団体の目的
|
共に自然を学んでその価値を知り、自然保護の活動を行うことに関する事業を行い、好ましい地球環境の持続に寄与することを目的とする。
|
|
団体の活動・業務
|
屋内及び野外での自然学講座・環境教育活動
自然保護、自然復元のための活動 自然環境・自然保護に関する調査研究 環境関連機器の開発と試験研究 環境保護に関する出版物の発行及び物品の販売 会報の発行 自然保護活動に必要な土地の借用または保有 その他この法人の目的達成に必要な事業 |
|
現在特に力を入れていること |
自然保護、再生の実践活動を、より充実した高い内容で行うこととともに、企業や各種団体からの一般参加者を積極的に受け入れ、活動や理念の裾野の拡大に努めたいと思っている。そのため、こどもや家族連れを対象にしたプログラムの充実に力を入れている。
|
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
定款の目的に沿った活動であれば、どんなことでも前向きに取り組んでいい期待と考えています。
平成23年度からは、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被災地域において、 (1)エコツアー、体験型ツアーの企画・実施による地域の自然特性の情報のとりまとめおよび観光産業の振興 (2)有機質資材の有効活用による環境改善 (3)アウトドアの知識や経験を活かした自然遊びの実践活動 についての活動を始めています。 |
|
定期刊行物 |
年会報「山から始まる自然保護」(年1回発行)
|
|
団体の備考 |
平成23年より、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被災地域での
(1)エコツアー、体験型ツアーの企画・実施による地域の自然特性の情報のとりまとめおよび観光産業の振興 (2)有機質資材の有効活用による環境改善 (3)アウトドアの知識や経験を活かした自然遊びの実践活動 についての活動を始めた。 平成25(2013)年6月、東京都へ本部所在地を移転しました |
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
・ヤフー株式会社(Yahoo!ボランティア・富士山森林復元活動へのインターネット募金)
・特定非営利活動法人夢&環境支援基金(高山植生モニタリング調査活動への2011年助成) ・株式会社共立理化学研究所、株式会社椿、日本生命保険相互会社、マウンテントラベル/ヒマラヤ観光開発株式会社(年会報への広告賛助・活動への協力など) ・社団法人日本損害保険代理店協会、 国際花と緑の博覧会記念協会、 セブン-イレブンみどりの基金 、 ゆうびんCSR・年賀寄附金 など(活動への助成) |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
・森林復元活動・里山再生活動(特に在来樹種の種子採取活動)における、東京農業大学 治山・緑化工学研究室との協働
・十三浜プロジェクト(津波浸水地での有機物の現地活用・リサイクル/建築物の製作など)における、日本工学院八王子専門学校との協働 ・高山植生モニタリング調査における、独立行政法人国立環境研究所との連携調査・情報交換 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
国立環境研究所と共同研究・調査(中央アルプス木曽駒ヶ岳、三ノ沢岳周辺の高山植生モニタリング調査)
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
・富士山の森林復元活動(静岡森林管理署との協定による)
・高山帯の植生モニタリング調査(国立環境研究所との連携・調査の一部受託) |
最新決算総額 |
500万円~1,000万円未満
|
会計年度開始月 |
1月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
理事会
|
会員種別/会費/数 |
正会員 年額5,000円 160人
講座会員 年額3,000円 30人 賛助会員 7名(団体含む) |
加盟団体 |
日本山岳会、日本自然保護協会、日本山岳ガイド協会
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
0名
|
0名
|
| 非常勤 |
0名
|
0名
|
|
| 無給 | 常勤 |
0名
|
0名
|
| 非常勤 |
14名
|
0名
|
|
| 常勤職員数 |
0名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
14名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
50名
|
||
報告者氏名 |
中村 華子
|
報告者役職 |
理事
|
法人番号(法人マイナンバー) |
8020005004227
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2025年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2026年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2025年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















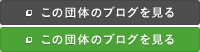
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する