|
公益社団法人ピースボート災害支援センター
|
団体ID |
1581077698
|
法人の種類 |
公益社団法人
|
団体名(法人名称) |
ピースボート災害支援センター
|
団体名ふりがな |
ぴーすぼーとさいがいしえんせんたー
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
ピースボート災害支援センター(PBV)は、被災地での災害支援活動や災害に強い社会づくりに取り組む公益法人です。「人こそが人を支援できるということ」をテーマに、すべての人々がお互いに助け合る社会を目指して、国内外の災害支援活動を展開しています。
誰しもが、自然災害に遭遇する可能性があります。 市民が助け合わなければ、もはや災害には立向えません。 いつ、どこで起こるか分からない災害は、 時に私たちを被災者にし、時に私たちを支援者にもします。 自分を守り、大切な人も守ります。 そして、少し遠くの「あの人」を支えます。 私たちは、被災者や被災地域の回復のために、 その文化や営みに寄り添い、支援者として自発的に関わる多様な人々の想いを 具体的に“役に立つカタチ”にしていきます。 みなさんと一緒に、「お互いさま」を共に歩みます。 その被災地域の人たちには、回復力があります。 困難な状況であったとしても、適切なサポートがあれば、未来に向かう一歩を踏み出せます。 ひとつとして、同じ災害はありません。 そして、ひとつとして、同じ支援のカタチもありません。 その時、その場所、その人たちに必要な支援を実施します。 ①国内外の災害支援 災害に見舞われた地域の回復ために、多様な支援者と共に、被災者のニーズに合わせた支援活動を展開しています。これまでにのべ11万人以上のボランティアと共に活動してきました。 ②防災・減災への取り組み 災害に強い社会を創るため、支援人材の育成、災害ボランティアトレーニング、家庭や地域の防災教育、ネットワーク構築をおこなっています。 ③東北への支援 東日本大震災以降、長期に渡り継続的な支援活動を実施してきました。 |
代表者役職 |
代表理事
|
代表者氏名 |
山本 隆
|
代表者氏名ふりがな |
やまもと たかし
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
169-0075
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
新宿区
|
|
市区町村ふりがな |
しんじゅくく
|
|
詳細住所 |
高田馬場1-29-20-1F
|
|
詳細住所ふりがな |
たかだのばば
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
kyuen@pbv.or.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-3363-7967
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
※土日祝定休
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
-
|
連絡先区分 |
-
|
|
連絡可能時間 |
-
|
|
連絡可能曜日 |
-
|
|
備考 |
-
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
840-0813
|
都道府県 |
佐賀県
|
|
市区町村 |
佐賀市
|
|
市区町村ふりがな |
さがし
|
|
詳細住所 |
唐人二丁目5番25号 TOJINシェアオフィス二号館
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
||
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
2011年4月19日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2011年4月19日
|
|
活動地域 |
日本全国および海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
40名
|
|
所轄官庁 |
内閣府
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
災害救援
|
|
|
福祉、地域・まちづくり、地域安全、国際協力、国際交流
|
|
設立以来の主な活動実績 |
「国内外での災害支援」「防災・減災への取り組み」「東北での活動」の3つを柱に、全国各地・海外で活動を展開。
●国内外の災害支援(主な活動) 【2011年】 東日本大震災 宮城・福島:台風12号被害・和歌山 【2012年】 新潟豪雪被害:九州北部豪雨:米国NYハリケーン「サンディ」 【2013年】 静岡、山口、岩手 大雨災害:台風26号 東京都大島町:フィリピン台風30号 【2014年】 山形県南陽市 大雨被害:広島市土砂災害 【2015年】 ネパール巨大地震:東北・関東豪雨災害 【2016年】 熊本地震 【2017年】 九州北部豪雨 【2018年】 西日本豪雨[平成30年7月豪雨]:北海道胆振東部地震 【2019年】 モザンビーク サイクロン・イダイ:台風15号・19号被害・福島千葉 【2020年】 オーストラリア森林火災:モーリシャス重油流出事故 【2021年】 静岡県熱海市土砂災害:8月豪雨災害・佐賀 【2022年】 ウクライナ人道支援:台風15号被害・静岡:インドネシア地震 【2023年】 トルコ・シリア大地震 【2024年】 台湾地震 【2024年】 東北大雨 【2024年】 能登半島地震・奥能登豪雨 ●防災・減災への取り組み 「災害ボランティア・トレーニング」…災害ボランティアの育成に取り組む。受講者数は、のべ8,700名以上。 「防災・減災教育プログラム」…家庭ごとの防災を学ぶ「わが家の災害対応ワークショップ」、地域の防災・減災力を引き出す「支援を活かす地域力ワークショップ」の研修を実施。 「国連防災世界会議」…第3回国連防災世界会議 in 仙台において、所属ネットワークであるJCC2015の事務局として、「市民防災世界会議」を実施。国連防災機関(UNDRR)をはじめ、海外の防災・減災NGOネットワークとも活動を展開する。 「国内ネットワーキング」…将来の災害に備えた連携・協働のため、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)、国際協力NGOセンター(JANIC)、ジャパン・プラットフォーム(JPF)、震災がつなぐ全国ネットワーク(震つな)、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)、防災・減災日本CSOネットワーク (JCC-DRR)、民間防災および被災地支援ネットワーク(CVN)などを通じたネットワーキングを行っている。 ●東日本大震災 東北での活動 宮城県石巻市・女川町を中心に、5年間で延べ9万人以上の災害ボランティア活動をコーディネート。救援物資の提供、避難所でのサポート、炊き出し、家屋・店舗の清掃、漁業支援などの緊急支援活動を行った後、仮設住宅入居者のサポート、復興街づくりのサポート、漁村部の復興支援を行う。福島県南相馬市の中学生らを対象とした保養と国際交流のプロジェクトも続けている。 ※2019年10月1日に、団体名称を「一般社団法人 ピースボート災害支援センター」に変更 ※2025年4月1日に、内閣府から「公益社団法人」に認定 |
|
団体の目的
|
当法人は、日本国内外において自然災害及び紛争や戦争などによる人道危機が新たに発生した場合、被災者が安定した状況で、尊厳をもって生存し回復するために、あるべき人道上の要請を最優先して、迅速かつ効果的かつ持続的に被災者を支援し公益性の高い事業および国際協力活動に取り組むことである。またそれを実行するため国内外の様々な組織と連携、協力し支援体制を整え目的を達成するために、次の事業を行う。
|
|
団体の活動・業務
|
1) 自然災害および紛争や戦争を起因とした被災地への緊急支援および復興に関わる人道支援事業
2) 研修および書籍や研修教材の頒布を通じた防災・減災に関わる認知向上と人材育成に関わる事業 3)人道支援に関わる様々な関係者と支援の質、安全管理、連携強化を図るためのネットワーク構築事業 4) 報告会、ウェブサイト運営、SNSおよびメールマガジン配信、メディアなどを通じた活動に関する情報発信や調査・研究および提言を通じた普及・啓発に関する事業 5) 支援活動に必要となる支援物資、資機材、車両などを維持管理する事業 6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
|
現在特に力を入れていること |
各地で、毎年のように発生する風水害や地震被害などに対して、迅速にスタッフを現地に派遣し、現地調査をもとに被災地域のニーズにあった多様な支援活動を実施している。平時には、災害支援の知見を活かした、防災教育や研修を行っている。
今後、首都直下地震や南海トラフ地震など大災害の発生が懸念されているなか、各関係機関や支援団体、企業などとのネットワーク作りに力を入れている。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
気候変動の影響などもあり、災害リスクが日本全国・世界各地で高まっている。いち早く現場に駆けつけ災害支援活動を展開するのはもちろん、平時から関係団体と連携・協働することで、被災者のニーズにきちんと応えられる全国的な体制づくりにも取り組みたい。また、そのためにはその仕組みを支える人材・組織の育成が必要となるため、災害ボランティア・トレーニング、防災・減災教育の取り組みをさらに広げ、避難所運営訓練や災害ボランティアセンターマッチングシミュレーションゲームなど、新しいメニューの開発にも力を入れている。
|
|
定期刊行物 |
-年次報告書…年1回発行
-メールマガジン…月1回発行 ー災害支援初動レポート/活動報告書…都度 |
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
●助成金・寄付
各被災地支援活動に対する企業・団体などからの助成金・寄付を多数いただいている。各年度ごとの助成元は、下記ホームページの活動報告書参照。 http://pbv.or.jp/about_pbv/ ●災害ボランティア 各被災地支援活動に対する企業・大学などからの社員・学生ボランティアの受け入れ・活動コーディネートを行っている。 |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
●被災地での支援活動
被災地支援には、地元団体との協働、外部支援団体の協働が欠かせないため、様々な連絡会に参加しながら活動を展開している。海外災害ではUNOCHAクラスターミーティング、国内災害では各地での情報連携会議へに参加。(東日本大震災(2011年)では石巻災害復興支援協議会、常総市水害対応NPO連絡会議(2015年)、熊本地震・支援団体火の国会議(2016年)など。) ●加盟ネットワーク・パートナーシップ https://pbv.or.jp/about_pbv/about_pbv_03 ●共同研究などで発行または出版等に協力した書籍・資料 https://pbv.or.jp/about_pbv ●第3回国連防災世界会議 in 仙台 国内のCSO104団体が集うネットワークJCC2015(2015防災世界会議日本CSOネットワーク)の共同事務局として、海外の災害支援NPOネットワークであるアジア防災・災害救援ネットワーク(ADRRN)、地球市民社会のための防災ネットワーク(GNDR)、ホワイロー委員会(Huairou Commision)とのMOUを締結し、本体会議における政策提言活動や市民防災世界会議を実施した。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
●協力企業団体
被災地支援には、企業・団体との協働、民間の外部支援団体の協働が欠かせないため、「ひと・もの・かね・情報」のニーズに合わせ、様々な企業・団体と協働している。 https://pbv.or.jp/collaborator ●企業ネットワークとの協働 緊急災害対応アライアンスSEMA 国民生活産業・消費者団体連合会(生団連) 民間防災および被災地支援ネットワーク |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
●被災地での支援活動
被災地支援には、地元行政との連携・協働が欠かせないため、役場担当者や災害対策本部との情報交換を行っている。また支援要請による被災者支援活動も展開している。東日本大震災時の宮城県石巻市での炊き出し支援(2011年)、熊本地震における益城町での避難所運営サポート(2016年) ●委託業務・協定など -外務省NGO研究会「防災分野における国際協力NGOが果たすべき役割」(2014年) -新宿区協働事業「地域防災の担い手育成(しんじゅく防災フェスタ)」(2016年-2018年) -熊本豪雨災害における球磨村村外避難所運営(2020年) -佐賀県及び公益財団法人佐賀未来創造基金と進出協定(2023年)など |
最新決算総額 |
1億円~5億円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
0円
|
|
|
| 寄付金 |
116,657,937円
|
|
|
|
| 民間助成金 |
459,981,454円
|
|
|
|
| 公的補助金 |
0円
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
14,323,101円
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
0円
|
|
|
|
| その他収入 |
237,059円
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
591,199,551円
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
112,555,570円
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
193,353,940円
|
|
|
| 内人件費 |
45,514,999円
|
|
|
| 次期繰越金 |
510,250,181円
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
203,497,107円
|
|
| 固定資産 |
337,242,545円
|
|
|
| 資産の部合計 |
540,739,652円
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
30,489,471円
|
|
| 固定負債 |
0円
|
|
|
| 負債の部合計 |
30,489,471円
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
112,555,570円
|
|
| 当期正味財産増減額 |
397,694,611円
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
510,250,181円
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
0円
|
|
|
| 受取寄附金 |
116,657,937円
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
459,981,454円
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
0円
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
14,323,101円
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
0円
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
237,059円
|
|
|
|
| 経常収益計 |
591,199,551円
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
193,353,940円
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
112,555,570円
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
510,250,181円
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
203,497,107円
|
|
| 固定資産合計 |
337,242,545円
|
|
|
| 資産合計 |
540,739,652円
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
30,489,471円
|
|
| 固定負債合計 |
0円
|
|
|
| 負債合計 |
30,489,471円
|
|
|
| 正味財産合計 |
510,250,181円
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
-社員総会:1回/年
-理事会:2回/年 ※その他必要に応じて臨時あり -事務局:1回/週を基本に必要に応じて |
会員種別/会費/数 |
災害支援サポーター:512名(2025年3月末時点)
|
加盟団体 |
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
2名
|
10名
|
| 非常勤 |
2名
|
26名
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 常勤職員数 |
12名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
40名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
11997名
|
||
報告者氏名 |
山本 隆
|
報告者役職 |
代表理事
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
2011年4月19日
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
その他
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
公益社団法人会計基準
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
公認会計士 今西浩之事務所
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|||
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|||
|
2021年度
|
|||
|
|
|||
|
2020年度
|
|||
|
|
|||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















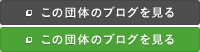
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する