|
特定非営利活動法人河北潟湖沼研究所
|
団体ID |
1662304383
|
法人の種類 |
特定非営利活動法人
|
団体名(法人名称) |
河北潟湖沼研究所
|
団体名ふりがな |
かほくがたこしょうけんきゅうじょ
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
河北潟及び河北潟地域において農業活動と自然再生が統一され、調和のとれた地域となることを目指し、以下の活動に取り組みます。
<河北潟湖沼研究所の地域活動の心得> 1.か 科学の目を地域にふやすことを望みます。 2.ほ 北陸の風土と文化、水郷の歴史をふまえて取り組みます。 3.く 苦難こそ研究の鍵、地域の問題をとらえます。 4.が 学問を地域に還元する社会づくりを目指します。 5.た 短期でなく長期ビジョンで目標をかかげます。 6.こ 湖沼の現状をおさえ、基礎データを蓄積します。 7.しょ 将来を展望し、循環型のしくみを模索します。 8.う 旨いものを、河北潟から生み出すことをねらいます。 9.けん 堅実に、理に叶うことに、最善を尽くします。 10.きゅう 休日に人々が潟の自然と関われる場を提供します。 11.じょ 情報を地域から集めて生かす研究機関としてはたらきます。 |
代表者役職 |
理事長
|
代表者氏名 |
高橋 久
|
代表者氏名ふりがな |
たかはし ひさし
|
代表者兼職 |
北陸水生生物研究センター 代表
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
929-0342
|
都道府県 |
石川県
|
|
市区町村 |
河北郡津幡町
|
|
市区町村ふりがな |
かほくぐんつばたまち
|
|
詳細住所 |
北中条ナ9-9
|
|
詳細住所ふりがな |
きたちゅうじょうな
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
info@kahokugata.sakura.ne.jp
|
|
電話番号
|
電話番号 |
076-288-5803
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~20時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金 土 日
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
076-255-6941
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金 土 日
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
||
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
||
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1994年10月14日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
1999年9月6日
|
|
活動地域 |
県内
|
|
中心となる活動地域(県) |
石川県
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
20名
|
|
所轄官庁 |
石川県
|
|
所轄官庁局課名 |
石川県NPO支援センター
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
地域・まちづくり、環境・エコロジー、市民活動団体の支援、食・産業、漁業、林業、学術研究(複合領域分野、その他)
|
|
設立以来の主な活動実績 |
1.農地における生物多様性に係る調査・提案における実績
1)河北潟西部承水路における外来植物の異常繁茂に係る調査(2002-) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/s10-1.pdf 2)河北潟干拓地における希少猛禽類の分布に関する調査 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/s11-2.pdf 3)河北潟干拓地における鳥獣害に関しての調査と提言(2003-) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/s6-3.pdf 4)河北潟の周辺農地における農薬使用の実態と野生生物への影響に関する研究(2012-) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/sougouken/s17_2.pdf 5)河北潟の再汽水化に関する研究(2016-) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/newsletter/vol25_1.pdf 6)河北潟の流域保全と流域連携に関する調査・研究と実践(2017-) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/pamph/ryuuikimap2020web.pdf 2.指針作成・研修会等に係る実績 1)河北潟将来構想の作成と発表(1999) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/news/kousou.html 2)河北潟と干拓地の将来を考えるシンポジウム(ワークショップ)(2002・2003・2009) 参考URL:http://kahokugata.sakura.ne.jp/pdf/vol8_4.pdf 3.農村環境向上に係る順応的管理等の実績 1)河北潟干拓地ビオトープの造成と経過観察(1998-2008) 2)津幡町アサザビオトープの設計と共同管理体勢の確立(1999-) 3)農業用水路に繁茂する外来植物の除去に関する順応的管理(2004-) 4.地域主体としての実践活動・技術開発における実績 1)矢板護岸の水路における水草の順応的管理に係る技術開発(2004- 2)河北潟外来植物対応方策検討会における主体形成に係る活動(2007-) 3)河北潟干拓地における農地・水・環境保全向上対策の取組みへの参加(2006-) 5.農地の環境保全につながる社会的自主事業 1) 潟と砂丘の循環事業とすずめ野菜事業(2011-) 2) 生物多様性の保全のための生きもの元気米事業(2014-) 3) 地域流通をつくり環境保全に積極的な農家を応援する金沢駅西ゆうぐれマルシェ(2105-) 6.出版事業 1) 研究紀要の発行(1998-) 2) 河北潟レッドデータブックの発行(2013) 3) 出版事業部としての市民科学出版の立ち上げ(2018-) |
|
団体の目的
|
河北潟は、1963年の国営干拓地事業によって大きくその姿を変えました。しかし、現在でも約4平方キロメートルの水面を有する石川県で最大の湖です。近年、この河北潟の水質の悪化が著しく、また活動を始めた1990年代前半には、湖岸のゴミ問題も顕在化していました。また、湖を埋めて誕生した干拓地は、減反政策のなかで畑地と畜産をおこなうべく入植が始まったものの、未売却地も多く残り、また入植した農家も畑作の難しさから経営困難に陥ったり、耕作放棄するものも見られ、荒れ地が目立つ状態でした。
こうしたなかで、河北潟の環境改善と干拓地振興のための地域住民による取組が始まっていました。この活動の中から、専門家を含めて河北潟の環境改善についての具体的な方法を検討する必要が指摘され、水質および生態系、親水性、干拓地のあり方、社会システム等についての調査研究を実施し、河北潟の環境問題の解決を通じて持続可能な社会の実現を目指す、地域に根ざした研究機関の設立を企画されました。1999年8月に石川県より認可受け、県内では最初の環境分野のNPO法人、河北潟湖沼研究所が設立されました。 |
|
団体の活動・業務
|
1.環境保全活動として、講座「河北潟自然保護学校」の開催や各種自然観察会を実施。
2.「河北潟と干拓地の将来を考える」、「河北潟の水辺を守るためには」等のシンポジウムを実施。 3.環境省いきづく湖沼ふれあい事業、農村景観・自然環境保全再生パイロット事業等の受託。関連して、農地の外来植物除去活動の実施。 4.過去に「内灘町生態系活用水質浄化実験施設」における水質浄化実験、河北潟干拓地水辺ビオトープの造成および経過調査を実施したことを契機に、生態系を活用した水質浄化と生態系の順応的管理にかかる調査と実践を継続している。 5.中国南京湖泊研究所および香港理工大学との共同研究の協定、日中共同湖沼浄化研究プロジェクト中間学術検討会(中国南京市)の開催、モンゴル環境視察団派遣等、国際的な研究連携を図っている。 6.河北潟の再汽水化に関する研究プロジェクト 7.農地としての流域保全に関する研究プロジェクト 8.ニュースレター、研究年報の発行 |
|
現在特に力を入れていること |
当研究所は、人と河北潟との関係を取り戻すこと、河北潟の自然とくらしの新しい再生を掲げている。
具体的な中期目標としては、 1)特に農業分野での地域産業との関わりを追求していく。外来種除去の活動と関連させて、地域における循環活動の事業化について展望する。潟の外来植物を堆肥化し砂丘農業に使用することを軸に産業との関わりをつくっていく。また、生産に引き続く販売の展開として、地域におけるまちづくりへの参加の可能性を追求しつつ、河北潟関連グッヅのアンテナショップの展開を展望する。 2)当研究所の本来の目的を達成する事業を展開する上でその可能性を大きく広げるために、専任職員を配置し、当研究所の目的と合致した事業の中で雇用者を有効に活用し、NPO活動がさらに進展する方向をつくる。 3)生産者団体を加えた地域連携活動に協力し、また牽引する役割を果たしていく。水田耕作を行う事業を地域連携の中で実施し、農業と周辺水辺管理のモデルを構築する。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
1.河北潟の生物多様性を守り、保全・再生することを通じて地域を活性化する。
(河北潟およびその周辺地域の環境保全と地域振興につながる研究と実践) 2.湖沼のあるこの地域において、地域を構成する多様な主体が参画することにより、自然環境と共生する持続可能な地域、将来を担う子供達の成長の場となる地域を再生させる。 (地域住民、地域企業、行政、研究者をつなぐ組織となり、地域環境保全・地域環境問題解決のための地域協働の要となる) 3.研究所として総合的に問題をとらえ、科学的に長期ビジョンをもって地域を導く (地域のシンクタンクとして機能すること) |
|
定期刊行物 |
河北潟総合研究 500部 年1回発行 http://kahokugata.sakura.ne.jp/kankoA.html
ニュースレター「かほくがた」1000部 年4回発行 http://kahokugata.sakura.ne.jp/kanko.html |
|
団体の備考 |
河北潟湖沼研究所は、環境分野のNPO法人として多分野にわたる活動をおこなっている。環境保全のための調査・研究活動などの非営利活動とともに、これらの活動を支えるための収益事業、そして広報や出版、イベントを通じて社会へのアピールなど、それぞれの部局が担当している。
【活動実績(過去1~2年間程度)】 平成22年4月~ 金沢市こなん水辺公園へ自然解説員を派遣 市民と当団体との窓口、市民が自然とふれあう場として機能(23年度観察会参加者346名) 平成22年4月4日 第71回河北潟自然観察会 開催(年6回を10年間以上実施) 河北潟の自然に興味を持つ市民の増加 平成22年6月17日 内灘町小学校2校へ自然保護授業の講師派遣 平成22年10月 河北潟カレンダーの発行 600部を販売・配布 平成22年11月23日 河北潟自然再生まつり企画参加 まつり全体参加者220名 平成22年11月26日~ 外来植物除去活動 延べ約100名が参加 平成23年2月26日 柴山潟の水辺を守る懇談会 開催 平成23年3月31日 河北潟湖沼研究所機関誌「河北潟総合研究」第14巻発行 研究成果を市民へ提供するとともに、全国の70あまりの研究機関・図書館に送付 平成23年10月4日 河北潟外来植物対応方策検討会にて調査結果を報告 行政機関・農業団体20団体以上が参加 平成23年10月30日 金沢市才田公民会主催講演会の講師派遣 約40名に講演 平成23年10月11日~ 河北潟セミナー開催(月1回程度) 毎回10~20名が参加 平成24年2月26日 柴山潟フォーラムに講演者2名派遣 平成24年4月~ 外来種堆肥を使った野菜生産の販売開始、無農薬稲作の試行開始 循環型社会づくり・環境保全型地域社会づくりの実践へ |
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
2010年度 いいね金沢環境活動賞 受賞
2012年度 日本水大賞未来開拓賞 受賞 2013年度 石川県環境活動功労者表彰 受賞 2014年度 生物多様性の10年認定連携事業 2014年度 生物多様性アクション大賞えらぼう部門受賞 2015年度 日本自然保護大賞保護実践部門受賞 セブン-イレブンみどりの基金(22年3月~23年2月) 損保ジャパン環境助成(23年9月~24年10月) 花博記念財団(24年4月~25年3月) トヨタ財団社会環境プログラム(24年4月~26年3月)(活動チームとして応募) パナソニックNPOサポートファンド組織診断助成(24年11月~25年5月) アクト・ビヨンド・トラスト「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」(25年4月~28年3月、31年4月~2年3月) 高木仁三郎市民科学基金(31年4月~2年3月) パナソニックNPOサポートファンドキャパシティビルディング助成(25年7月~26年6月) 地球環境基金助成(26年4月~) ゆうちょエココミュニケーション(2年4月~) エフピコ環境基金(3年4月~) |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
チクゴスズメノヒエの除去活動については、2005年から2年間は、環境省のモデル事業の指定を受けて河北潟湖沼研究所が主催する事業として実施した。この活動が評価され、07年には、農水省(北陸農政局)が河北潟湖沼研究所のアドバイスを受けながら関連する農業団体を取り込んで、除去活動の試行を行った。08年と09年には、再び河北潟湖沼研究所が事業主体となって農水省のパイロット事業の指定を受けるとともに、事業を推進するための連絡組織と行政11団体、農業団体3団体、NPO2団体、大学1団体の17団体からなる「河北潟外来植物対応方策検討会」が発足し、100名規模の活動を展開した。10年には、河北潟湖沼研究所も参加するグリーン・アース河北潟において10名を緊急雇用しての手作業による除去活動も行った。11年 度からは、10の農業団体からなる「河北潟の水辺を守り隊」の発足にあわせて、除去活動の主体をここに移し、広く農家の参加を得て100名規模の活動を継続している。活動の進展により、農家が水路で農薬を使わなくなったり自主的に自分の地域で外来植物の除去活動を行うなど、自主的主体的な活動も確認されている。同時に、在来植物の保全活動にも農家が関心を持ち、水路の除草を控えたりするようになってきた。このように河北潟地域では、外来植物の市民による除去活動が定着し、特に農地の水路の生物多様性の保全に農業関係者
が積極的に取り組むようになってきている。ある素堀の水路において地域の農家を巻き込んだ除去活動を行う中、高齢者がひとりで農業を行っている実態や協働の取り組みに勇気づけられたことが農家から話されたことから、除去活動を発展させ、市民参加による米作りと協働管理による継続的な水路の保全活動を進めている。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
河北潟干拓土地改良区が事務局を務める「グリーン・アース・農地・水・環境保全組織」のメンバーとなっている。
|
行政との協働(委託事業など)の実績 |
1)平成17年度及び平成18年度 環境省 いきづく湖沼ふれいあいモデル事業
業務内容:地域主体による水域環境の順応的管理の実践活動とシンポジウムの開催 2)平成20年度及び平成21年度 農水省 農村環境・自然環境保全再生パイロット事業 業務内容:農地における順応的管理手法の検討とシンポジウム、研修会、検討会等の実施 3)こなん水辺公園案内解説等業務委託 金沢市緑と花の課 平成21年より継続 4) 平成22年度・23年度石川県民間提案型雇用創出事業「親水性を伴った水質浄化手法の検討に係る取組」 業務内容:石川県3湖沼の湖岸の植生調査と水質調査 5)平成25年度「柴山潟及び周辺水田のラムサール条約追加登録に向けた希少水生植物の調査業務委託」 6)平成26年度~「北潟外来植物利用に関する調査業務委託(河北潟干拓地内)」 |
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
有
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
256,000円
|
328,000円
|
400,000円
|
| 寄付金 |
229,707円
|
753,763円
|
1,000,000円
|
|
| 民間助成金 |
2,920,000円
|
3,823,000円
|
9,310,000円
|
|
| 公的補助金 |
50,000円
|
50,000円
|
50,000円
|
|
| 自主事業収入 |
5,852,345円
|
5,966,554円
|
8,700,000円
|
|
| 委託事業収入 |
6,379,933円
|
5,081,472円
|
4,372,000円
|
|
| その他収入 |
589,683円
|
635,652円
|
500,030円
|
|
| 当期収入合計 |
16,277,668円
|
16,584,441円
|
24,332,030円
|
|
| 前期繰越金 |
5,386,963円
|
6,796,613円
|
5,387,435円
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
14,797,018円
|
17,922,619円
|
24,328,454円
|
| 内人件費 |
7,282,857円
|
9,684,168円
|
10,050,000円
|
| 次期繰越金 |
6,796,613円
|
5,387,435円
|
5,391,011円
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
8,475,829円
|
9,143,977円
|
| 固定資産 |
0円
|
0円
|
|
| 資産の部合計 |
8,475,829円
|
9,143,977円
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
1,679,216円
|
3,756,542円
|
| 固定負債 |
0円
|
0円
|
|
| 負債の部合計 |
1,679,216円
|
3,746,542円
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
5,386,963円
|
6,796,613円
|
| 当期正味財産増減額 |
1,409,650円
|
-1,409,178円
|
|
| 当期正味財産合計 |
6,796,613円
|
5,387,435円
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
256,000円
|
328,000円
|
400,000円
|
| 受取寄附金 |
229,707円
|
753,763円
|
1,000,000円
|
|
| 受取民間助成金 |
2,920,000円
|
3,823,000円
|
9,310,000円
|
|
| 受取公的補助金 |
50,000円
|
50,000円
|
50,000円
|
|
| 自主事業収入 |
5,852,345円
|
5,966,554円
|
8,700,000円
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
6,379,933円
|
5,081,472円
|
4,372,000円
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
589,683円
|
635,652円
|
500,030円
|
|
| 経常収益計 |
16,277,668円
|
16,584,441円
|
24,332,030円
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
14,797,018円
|
17,922,619円
|
24,328,454円
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
5,386,963円
|
6,796,613円
|
5,387,435円
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
6,796,613円
|
5,387,435円
|
5,391,011円
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
8,475,829円
|
9,143,977円
|
| 固定資産合計 |
0円
|
0円
|
|
| 資産合計 |
8,475,829円
|
9,143,977円
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
1,679,216円
|
3,756,542円
|
| 固定負債合計 |
0円
|
0円
|
|
| 負債合計 |
1,679,216円
|
3,746,542円
|
|
| 正味財産合計 |
6,796,613円
|
5,387,435円
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
理事会及び社員総会
|
会員種別/会費/数 |
一般会員12000円×22名、法人会員24000円×1名、友の会会員3000円×30名
|
加盟団体 |
河北潟自然再生協議会
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
0名
|
3名
|
| 非常勤 |
0名
|
4名
|
|
| 無給 | 常勤 |
1名
|
0名
|
| 非常勤 |
13名
|
0名
|
|
| 常勤職員数 |
3名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
20名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
40名
|
||
報告者氏名 |
高橋 久
|
報告者役職 |
理事長
|
法人番号(法人マイナンバー) |
8220005007283
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
2023年5月20日会計監査を実施し、適正に処理されてていることを確認した。
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
2021年度
|
|||
|
2020年度
|
|||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
2021年度
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















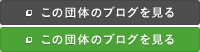
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する