|
小児交互性片麻痺 親の会(AHCの会)(任意団体)
|
団体ID |
1723537575
|
法人の種類 |
任意団体
|
団体名(法人名称) |
小児交互性片麻痺 親の会(AHCの会)
|
団体名ふりがな |
しょうにこうごせいへんまひ おやのかい えーえいちしーのかい
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
小児交互性片麻痺という疾患自身が非常に稀な病気で、現在、診断されているのは日本全国で50人程度です。しかし、専門医以外にはほとんど知られていないという中で、潜在的には2~3倍の患者がいると推測されています。私たちの親の会は現在28家族ですが、活動の重点は、①現在の会員患者・家族の交流と、②病気の知名度を上げ、一人でも多くの同じ病気の仲間との出会いを作ることです。そのため、患者・家族の集まる全国交流会(年一回)、地域交流会(随時)の開催や、小児神経学会などでのパンフレット配布やプレゼンなどの宣伝活動を積み重ねてきました。また、小児慢性特定疾患への認定を求める活動や、現在日本では販売が中止されている「フルナリジン」(会員は個人輸入に頼って入手しています)の販売再開を求める活動などに取り組んできましたが、2015年に小児慢性特定疾患に、2016年に難病認定を受けましたので、いよいよこれからは会員が安心して社会生活を送るための活動とフリナリジン販売再開の活動に力を入れていきたいと思っています。
|
代表者役職 |
代表
|
代表者氏名 |
川嶋 典明
|
代表者氏名ふりがな |
かわしま のりあき
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
-
|
都道府県 |
滋賀県
|
|
市区町村 |
-
|
|
市区町村ふりがな |
-
|
|
詳細住所 |
-
|
|
詳細住所ふりがな |
-
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
-
|
|
電話番号
|
電話番号 |
070-1263-2558
|
連絡先区分 |
自宅・携帯電話
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
土 日
|
|
備考 |
問い合わせ担当:ことう
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
-
|
連絡先区分 |
-
|
|
連絡可能時間 |
-
|
|
連絡可能曜日 |
-
|
|
備考 |
-
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
|
|
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
|
|
寄付 |
|
|
ボランティア |
|
|
関連ページ |
|
|
閲覧書類 |
|
|
設立年月日 |
2003年8月21日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
|
|
活動地域 |
複数県
|
|
中心となる活動地域(県) |
大阪府
|
|
最新決算総額 |
100万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
4名
|
|
所轄官庁 |
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
子ども、青少年、障がい者、福祉、保健・医療、国際交流、行政への改策提言
|
|
設立以来の主な活動実績 |
2003年:親の会設立。国立精神・神経センター病院佐々木先生の協力で第1回総会。会報発行開始。
2004年:フリナリジンの販売再開に向けた署名活動や薬の有効性を綴った手紙等で、参議院・衆議院の厚生労働委員会、厚生労働省、小児神経学会へ協力要請。 2006年:九州女子短大松本先生の現況調査に協力。 2007年:小児慢性疾患事業認定の嘆願を厚生労働省に提出。 2008年:日本小児神経学会・日本てんかん学会との連名で難病認定の要望書を厚生労働省に提出。 2009年:九州女子短大松本先生の現況調査に協力(2回目)。 2010年:国立精神・神経センター病院佐々木先生の現況調査に協力。 2012年:海外親の会代表来日、交流会開催。 2015年:小児交互性片麻痺の新パンフレットを発行。 |
|
団体の目的
|
本会は会員が、安心した社会生活を送ることができるよう相互に協力し、福祉の増進、会員の研修・親睦をはかることを目的とする。
|
|
団体の活動・業務
|
会員活動としては、会員数も少なく財政規模も小さいため、また会員が全国に散らばっている現状から、互いに交流し親睦を深める全体会(関東、関西で隔年開催)は年1回の開催とし、その他は年2回発行する会報への投稿と親の会のメーリングリストで情報交換と状況報告をしています。またホームページの開設とパンフレットを作成し、広くこの病気について知ってもらう活動も行っています。
|
|
現在特に力を入れていること |
この病気の予後は悪いのですが、病状はひとによって異なるため、必要な支援やその程度にはかなりの幅があります。そのため、会員も現状、課題は個々人で対応したり、悩みや不安を抱え込んでしまっている状況があるので、会員相互の情報交換とノウハウ共有をより活発化して、必要な支援・具体的な支援につなげることに力を入れたいと思っています。それが本人や家族が安心して社会生活を送れたり、少しでも自立した生活が送れることにつながると考えています。
また、医師でさえ知っているひとが少ない稀有な病気のため、対外的にこの病気およびその特性、本人の困り感などをもっと広く一般に認知してもらう活動と、現在販売停止になっているフルナリジンの販売再開の活動は継続して行っていく予定です。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
|
|
定期刊行物 |
AHCの会会報(年2回発行、会員対象約30部)
|
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
いのちの輝き毎日奨励賞(2014年、2015年)
|
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
2008年、厚生労働省へ「小児交互性片麻痺に関する要望書」を日本小児神経学会及び日本てんかん学会と協同で提出。
NPO難病のこども支援全国ネットワーク親の会連絡会関西部会に定例参加。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
国立精神・神経センター病院佐々木先生の現況調査に協力(2003年、2010年)
九州女子短大松本先生の現況調査協力(2006年、2009年) |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
|
最新決算総額 |
100万円未満
|
会計年度開始月 |
4月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | 2025年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々年度)決算 | 2024年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
|
会員種別/会費/数 |
|
加盟団体 |
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
4名
|
|
|
| 常勤職員数 |
|
||
| 役員数・職員数合計 |
4名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
|
||
報告者氏名 |
|
報告者役職 |
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2024年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|||
|
|
|
|
|
|
2020年度
|
|||
|
|
|
|
|
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2025年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















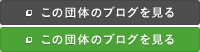
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する