|
認定特定非営利活動法人脳脊髄液減少症患者•家族支援協会
|
団体ID |
1497126761
|
|
法人の種類 |
認定特定非営利活動法人
|
|
団体名(法人名称) |
脳脊髄液減少症患者•家族支援協会
|
|
団体名ふりがな |
のうせきずいえきげんしょうしょうかんじゃかぞくしえんきょうかい
|
|
情報開示レベル |
|
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
脳脊髄液減少症の全ての情報 最新の情報を得る事ができる唯一の団体
国(各省庁) 地方 厚生労働省研究班 脳脊髄液減少症研究会所属の医師の面々 全国の患者会 マスメディアとも連携しています 日本脳脊髄液漏出症学会 https://js-csfl.main.jp/ アピールポイントは47都道府県公式HPと当会HPが相互リンクをはっている事 https://csf-japan.org/japanese/link.html 国 厚労省 国土交通省 文部科学省ともリンクを貼る https://csf-japan.org/japanese/link.html ※(市町村公式HPとも300以上の行政とリンクを貼っている) 行政ー医学界ー立法府ー認定NPOが うまくかみあう事で 社会問題を解決するKNOW-HOWのモデルの構築となる。 先駆的な取り組み、または、ユニークな手法により、今後、他のモデルとなる事業 社会のしくみの変革 前例にとらわれない方法により、旧来のしくみを変えていく事業 社会的インパクトの創出 取り組む社会課題が明確かつ、成果の波及効果が大きい事業を目指していける団体であると自負している |
代表者役職 |
代表理事
|
代表者氏名 |
中井 宏
|
代表者氏名ふりがな |
なかい ひろし
|
代表者兼職 |
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
649-6339
|
都道府県 |
和歌山県
|
|
市区町村 |
和歌山市
|
|
市区町村ふりがな |
わかやまし
|
|
詳細住所 |
弘西104
|
|
詳細住所ふりがな |
ひろにし
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
staff@npo-aswp.org
|
|
電話番号
|
電話番号 |
073-461-0317
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~17時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
出張が多いため事務所にいない事が多い 07050813559に御電話いただければつながります
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
042-325-8225
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 金 土 日
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
185-0002
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
国分寺市
|
|
市区町村ふりがな |
こくぶんじし
|
|
詳細住所 |
東戸倉2丁目12-46コーポ板倉201号
|
|
詳細住所ふりがな |
ひがしとくら
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
||
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
|
|
設立年月日 |
2002年5月15日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
2002年8月27日
|
|
活動地域 |
全国
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
6名
|
|
所轄官庁 |
和歌山県
|
|
所轄官庁局課名 |
和歌山県環境生活部県民局県民生活課県民活動団体室
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
|
|
|
子ども、障がい者、福祉、保健・医療、国際協力、就労支援・労働問題、消費者保護、市民活動団体の支援、行政監視・情報公開、行政への改策提言、学術研究(医学、歯学、薬学)、その他
|
|
設立以来の主な活動実績 |
2023年度版も本疾患はTV報道、著名人の告知などメディアを騒がせた。その記事には多くの共通点があった、それは「この疾患で周りの無理解で悩んだ、是非誰もがなる疾患である、多くの方に知ってもらいたい」。
2016年4月ブラッドパッチ療法の健康保険適用実現。 2002年交通事故後に難治性のむち打ち症(全体の5%)で悩む方の多くは脳脊髄液が漏れ出す事が原因と訴えた医師がいた。代表理事である中井の主治医の篠永正道医師(当時、平塚共済病院脳神経外科部長)。日本国内では特に交通事故後のむち打ち症の治療にあたる医師は整形外科医が多く、整形外科医領域では外傷による脳脊髄液の漏出はないという考えでした。 しかし、2000年頃から急速に発達した医療機器により、世界では外傷による脳脊髄液の漏れは十分ありえると論文を通じ報告が出るようになる。しかし、外傷による髄液漏れの報告はほぼ皆無。この交通事故後の難治性のむち打ち症の原因の一つが脳脊髄液漏れと考えは世界初でした。 当時、外傷により様々な症状で仕事もできず苦悩していた中井が、篠永医師の考えに賛同し検査を受けたところ大量の脳脊髄液の漏出が発見され、当時、国際的スタンダードな脳脊髄液の漏出を止めるブラッドパッチ療法を実施。急激な改善をみせます。 2007年から中井はネット上で「むち打ち症患者応援ページを開設」。そこで知り合った仲間にこの情報を発信し、ホームぺージを通じ100名が篠永医師の診断を受け、80名が患者と診断され、そのうち70%以上の患者が大きく改善し、次第に、この病気の啓発をめざすNPO法人設立の声が高まり、中井を代表とし篠永医師も参加し、2002年8月27日に法人枠を取得。その後、2003年には20数名の医師からなる脳脊髄液減少症研究会(篠永会長)が発足。2023年度 一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会設立 医師130名参加 https://js-csfl.main.jp/その反面、脳脊髄液の外傷による漏出の考えは、一部の医師が騒いでいるだけだと酷評する医師もいる。 患者数が増え、改善する人は30,000人、多くの患者は交通事故を起因とする為、損保業界との間で裁判が絶えず行われます。 損保会社は事故による脳脊髄液の漏出はありえないと訴えます。2016年に病気の保険適用は決定し、国は交通事故でこの病気が発症する事を認めました。しかし、実質、自賠責保険を運営する損保会社がこの病気を認めないという矛盾が起こっています。https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/trafficaccident.pdf 国土交通省自動車局(国土交通相)との協議の場で解決を目指している最中です。 専門家が徐々に増える一方、劇的に増加しない理由として診療報酬点数の低さがあります。人件費、造影剤、医療器具、手技量全て込みで8,000円。この問題にも取り組んでいます。その成果が2024年厚労省医務課の審議で決定する予定 その中で多くの国民が点数を上げて欲しいと地元行政にうったえ現在R5.10現在20道府県議会50市議会で点数をあげる地方議会から国にあげる意見書として採択されている。詳細はこちら http://www.npo-aswp.org/ikensyo |
|
団体の目的
|
(目的)会の定款より
本会は交通事故やスポーツ障害若しくは何らかの衝撃を受け、鞭打ち症になった患者(以下患者)に、長期の鞭打ち症を克服した会員が、有効な治療方針を助し患者の不安をのぞき、患者の健全な生活保持を支援することを目的とする。 また、長期に渡る症状の原因として、医学的に「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)」という病態が深く関与することがわかってきている。 しかし病態の知名度が低いため、検査及び治療を受診できる施設は、ごく限られている現状である。そこで会員同士の相互協力のもと、市民や団体等に助言や協力をする。また、次世代の患者のために完全で安心できる治療システムの確立を支援し、健全な国民生活の確保を応援する。 |
|
団体の活動・業務
|
2023脳脊髄液減少症患者支援体制構築(実施中)
1.脳脊髄液減少症シンポジウム事業 2.政策提言に向けた準備 3.公的機関との連携 4. 新型コロナウィルス後遺症及び各種脳脊髄液減少症患者調査 委託準備 5.患者相談 1について計2回/年の実施予定 10月8日兵庫県と共催でシンポジウム開催170名定員を超える 会議となった2回目も尾道市との共催にて尾道市役所2階でハイブリッド形式で開催する予定 2〜3 現状 スポーツ庁金融庁厚労省国土交通省文部科学省と連携をしている 4一般社団法人 日本脳脊髄液漏出症学会と連携し会員130名(医師)コロナウィルスおよびワクチン後遺症と脳脊髄液減少症の関係についてアンケートを実施、未だ解析できる数のデータが集まっていない。 5患者相談、医療の向上とともに完治率が高まってきている、その分相談は減っているが、交通事故の相談件数は増加傾向にある 相談事業について(ほぼ毎日Zoomでオンライン相談実施中)http://www.npo-aswp.org/catego2-04.html 実質、専門医が少ないため、かかった病院で軽くあしらわれ、「あなたはこの病気でない」という患者が、自身の症状から納得いかず、当会でZoom相談を受け、専門医にかかり改善完治する例があとを絶たない。 更に厚労省との直接リンク https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nanbyo/100402-1.html 文部科学省との間接リンク http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353640.htm 国土交通省との間節リンク http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/other/data.html 金融庁と連携し 脳脊髄液減少症相談フォーム 開設 http://www.npo-aswp.org/catego5-06.html |
|
現在特に力を入れていること |
現在もっとも力をいれている活動は 2023年度
「今後の活動の方向性・ビジョン」に詳しく書きましたが、世界でも本疾患の診断を注意しながら行うべきであるという警告論文が世界5大誌に掲載されました。 1) 様々な不定愁訴で悩む患者の中にこの疾患が隠れている 2) 小児・若年者の不登校性の中にこの疾患が隠れている(黒岩知事と面談神奈川県では調査開始予定) 2023年度小児・若年者の研究が引き続き決定しました。当会の大臣要望によって、また2016年度から研究が行われていますが、主だった成果を上げていない。厚労省から意見を求められ、具体的に研究方法を明示しました。今後、厚労省とも連携を取ることとなりました。 全国70万人いるとされる医学的要因による不登校性(OD・POTS) この病気と脳脊髄液減少症との深い関与がある事がわかってきました。 国と連携、研究班との連携、意見交換をしっかり行なっていく事が重要となる。 3) 精神的な病気(うつ症状)の中にこの疾患が隠れている 4) 交通事故後遺症で悩む患者の中にこの疾患が隠れている 5) 新型コロナウィルスの後遺症で悩む一部の患者にこの疾患が隠れている コロナと脳脊髄液減少症の関連が数多く国内で報告されるようになりました。非常に重要であり、国と連携する事が重要です。コロナ、もしくはワクチンが直接の後遺症の引き金となるのではなく、脳の視床下部(自律神経)を司る部位にワクチン及びウィルスが影響を与え、髄液の産生が少なくなり、脳脊髄液減少状態となるのではないかとのこと。2022〜2023年度内でコロナ後遺症候群の患者に対し脳脊髄液減少症の治療を施し、改善される症例が数多く出るでしょう。この世界的要素をまとめ発表する事が重要です。 こういった事実を様々な活動で啓発してきたが、今も変わりません。 今後はさらに「新型コロナウィルスの後遺症で悩む一部の患者にこの疾患が隠れている」という情報も発信する予定です。 1) 医療の基礎となる医師の確保 2) 安心して医師が活動できる日本脳脊髄液漏出症学会の安定軌道の協力 3) 安心経営ができる健康保険医療点数の確保 4) 超党派・脳脊髄液減少症対策議連の確保 5) WEBによる情報発信作業 6) そして顔を見ながらの相談業務(Zoomオンライン相談等) 7) 新しい交通事故患者救済法の設置 1)〜5)の活動は地道な作業であるが10月22日現在、待ったなしで毎日行われています。患者にとっては人生がかかっている問題ばかりである。6)の相談に関しては、相談内容についてもっと内容を深く理解いただけるように工夫していきます。 7)2023年度追記版 新しい交通事故患者救済法の設置に関して、これは絶対重要と感じます。何の罪もない人間が突如、病気となり、その保証(自賠責保険支払い) 病名を聞いただけで打ち切ってきます! 異常です。当該経験者しか理解できないでしょう。 昭和30年から何も変わっていない。自賠責保険の問題点に対し様々な出版物が出始めています。その共通点が、「いつ、どこで、だれが、どのように」という審査の過程がブラックボックスで開示が一切できない状況を指摘しています。残念ながら国会議員、大臣経験者、官僚までその現場の事実を知りません。理解させていく対話が重要です |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
「ビジョン国内版」(2023年追加分)
現在本疾患の専門医が増えない最大の理由、医療点数800点(8000円)危険な部位に針を刺すため、ほぼ全例X線透視下で治療が行われている。しかしこの針セットだけで2000〜3000円になる。透視下を加えると軽く8000点を超えて赤字になる。これでは病院が増えない。2024年に向けて点数が増え、多くの病院が治療開始し多くの患者が救済される事 そうする事で石川県が予算をつけ2024年めでに拠点病院を設置する予定、他府県でも同じ動きが開始されると思われる。 「ビジョン国内版」(2022年追加分) 世界でも脳脊髄液減少症に関わる警鐘が鳴り始めています。英国の医師Gが世界中の髄液漏れを調査。「実際の病名(髄液漏れ)と診断名が違うケースが非常に多い、注意深く髄液漏れを診断しなければならない」というレポートが世界3大医学誌であるJAMA(ジャーナル・オブ・アメリカン・メディカルアソシエーション)に投稿されています。詳細は当会会報34号に記載しました。 最近の報告で、諸外国の場合、実際の病名(髄液漏れ)にたどり着くまで平均13ヶ月と報告されています。わが国では世界に比べ若干短い気がします。これは当会を含めた医師グループの活躍です。 2022年~23年は、より多くのコロナ後遺症と脳脊髄液減少症の関連の症例が国内で蓄積されることでしょう。この件も国に報告しなければいけません。 脳脊髄液については近年、流動動態のLIVE映像が撮影され、髄液の作用が解明されつつあります。脳脊髄液減少症の診断基準も演繹法に基づき、6年かけて作成されましたが、患者全体の10%しか救済できないものとなっています。しかし、一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会の所属医師140名が互いの知見を交換しあい、厚労省基準に当てはまらない患者の多くの方が最新の知見により改善しています。 学会に所属する医師の増加が問題解決となる為、今後も啓発を行っていきたい。 司法の場でも同じ事が言えます。昭和30年に交通事故後の患者救済のため設立された自賠責法。 事故に遭われた患者の症状に合わせて、後遺症が残るケースは「病名に関係なく、患者の症状」で等級を決める事になっています。しかし現実は「病名」で決められている傾向があります。 現在、当会は上記の対策として、監督省庁の国土交通省と定期会議を進め、今後金融庁とも会議を行い、問題の本質を見極め、本来の患者救済を目指しています。官僚、大臣経験者、国会議員まで自賠責の問題点を理解していない事がわかりました。丁寧に時間をかけ対話形式での説明が必須となります。自賠責保険法は諸外国に遅れをとっています。 本来、治療で良くなり社会復帰が可能となる方でも、治療に巡り合えず生活面で社会保障に頼らざる方も少なくありません。経済的損失、社会保障費の増大につながっています。 また本来、重度の症状により国の管轄である自賠責保険では十分な保障を得るはずが、例え患者が障害者1級と認定されても、自賠責保険では後遺障害等級非該当となるケースも脳脊髄液減少症患者の場合少なくありません。このような矛盾に向き合い患者救済を目指します。 「2021年追加分」 患者相談は毎日のようにZoom相談を実施しています。患者それぞれの窮状は大変で、特に交通事故患者の窮状は、信じられないような現場の声をよく耳にします。現在、政党では公明党が唯一政策としていますが、与党である自民党にも政策Gを作っていただかなければなりません。特に自賠責保険の制度は残しつつ、新たな自動車事故救済法が必須であると感じています。 「ビジョン国外版」(2021年追加分) 世界の最新の状況は「ビジョン国内版」(2021年追加分)に書きました。 それゆえに日本の最新知見「脳脊髄液減少症」を世界発信し、多くの方を救済しなければいけない、意義がここにあります。 本年2021年一般社団法人(申請準備中)日本脳脊髄液漏出症学会が設立されました。 ここでは来年の事業として症例登録を開始する予定であるとの事。過去、任意団体(日本脳脊髄液減少症研究会)であったが、来年度〜再来年度中に法人化を終える予定。 「ビジョン小児・若年者版」 AMED予算で研究中の埼玉医科大学病院の研究成果の一つとして、不登校生の病的な最大原因「起立性調節障害、体位性頻脈症候群」の患者群の中で30%が「脳脊髄液減少症」という結果を予測しています。 小児学会によると「起立性調節障害、体位性頻脈症候群」の患者群は小児では軽症例を含めると中高学生の約10%となっています。各学年約 12 万人 (中高生合計で約70万人)と推定されます。欠席を繰り返し不登校状態に陥る重症例は約1%であり、全国で7万人と推定されるため、小児若年者の脳脊髄液減少症患者数は現時点で現状21000人と予測されます。 解決法については「現在特に力を入れていること」で記載しました。 我が国では科学的検査(MRI CT、その他)に頼る医師が多く、また、小児科医ではほぼ日頃経験しない「硬膜外への注射(生理食塩水パッチ)」を施述する事は、ほぼ機会がありません。よって小児科の脳脊髄液減少症の専門医が増えない状況にあります。 様々な手法、関係団体と協力し小児科医の脳脊髄液減少症に対する知名度をあげ、専門医を増やす事に全力を傾け、未来ある子供達を救済します。 小児科医に増加の解決策は、まず国で知見を固めるための研究を実施すること。2016年度から大きな成果を上げられていませんが、具体的な研究法を国と協議し、提案していくことになりました。 |
|
定期刊行物 |
会報 2〜3回/年 刊行しています
|
|
団体の備考 |
|
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
第九期2022脳脊髄液減少症患者支援体制構築
年度2023年度 事業費総額: ¥1,250,000 助成金額: ¥1,000,000 1.脳脊髄液減少症シンポジウム (1)時期:通年(計2回) (2)場所:専門医がいない地方等 (3)参加者:100名(一般、医師、行政関係者、弁護士、患者、議員) (4)内容:診療報酬点数の説明、新型コロナウィルスの後遺症の説明、その他小児・若年者の研究状況の説明、自賠責保険法の改善の必要性の説明 2.政策提言に向けた準備 (1)時期:通年 (2)場所:東京都千代田区 (3)参加者:関係省庁担当者、医師 (4)内容:シンポジウムの開催等 3.公的機関との連携 (1)時期:通年 (2)場所:各省庁等 (3)参加者:国会議員、地方議員、地方からの患者 (4)内容:制度改革の素地を作る 4.新型コロナウィルス後遺症及び各種脳脊髄液減少症患者調査 委託準備 (1)時期:通年 (2)場所:兵庫県明石市(日本脳脊髄液漏出症学会本部) (3)参加者:専門医 (4)内容:研究の内容、データ集積の方法等の検討 5.患者相談(情報発信及びデータベース稼働含む) (1)時期:通年 (2)場所:各所 (3)参加者:相談員 (4)内容:患者の社会保障、裁判、年金、交通事故、その他病気に関わる全体 第八期2022脳脊髄液減少症患者支援体制構築 年度 2022年度 事業費総額: ¥1,250,000 助成金額: ¥1,000,000 事業内容 1.脳脊髄液減少症シンポジウム事業 (1)時 期:年2回 (2)場 所:四国、九州、議員会館 (3)参加者:100名(一般、医師、行政関係者、弁護士、患者、議員) (4) 内容:診療報酬点数の説明、新型コロナウィルスの後遺症の説明、その他小児・若年者の研究状況の説明 2.患者相談事業 (1)時 期:通年 (2)場 所:オンライン (3)参加者:相談員 (4)内 容:患者の社会保障、裁判、年金、交通事故、その他病気に関わる全体 3.公的支援制度に向けての関係者会議の実施 (1)時 期:通年 (2)参加者:国会議員、地方議員、患者他 (3)内 容:公的支援制度確立に関する打ち合わせ他 第七期脳脊髄液減少症患者支援体制構築 団体名 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会 年度 2021年度 事業費総額: ¥1,350,000 助成金額: ¥1,080,000 事業内容 1.相談事業 (1)時 期:通年 (2)内 容:病気の説明、相談窓口の情報等 (3)配布先:患者、保健所、教育委員会等 (4)部 数:相談員との連携、相談マニュアル(1,000部)配布 2.データベース普及活動 (1)時 期:通年 (2)場 所:残り1県庁(山梨県) (3)対象者:教育長 (4)内 容:啓発・交渉(PDF版配布) 3.47都道府県(保健所、難病支援センター)への相談窓口開設 (1)時 期:2021年9月~2022年3月 (2)参加者:地方相談員、常勤2名 4.脳脊髄液減少症シンポジウム準備及び開催 (1)時 期:通年(計2回) (2)場 所:四国または九州、議員会館 (3)参加者:100名(一般、医師、行政関係者等) 第六期 脳脊髄液減少症患者支援体制構築 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会 年度 2020年度 事業費総額: ¥2,630,000 助成金額: ¥2,100,000 事業内容 1.相談マニュアル等の作成配布 2.官民連携データベース普及活動及び医療難民啓発活動 3.専門相談員3名養成事業 4.脳脊髄液減少症シンポジウム事業 5. シンポジウム準備会議 第五期 脳脊髄液減少症データベース普及と小児患者への啓発 1.脳脊髄液減少症シンポジウム (1)時 期:通年(計3~4回) (2)場 所:議員会館、大阪府、広島県、九州 (3)参加者:100名(一般、医師、行政関係者、弁護士、患者、国会地方議員(超党派)) 2.官民、半官民(認定/財団)連携、データベース普及活動及び医療難民啓発活動 (1)時 期:通年 (2)場 所:20府県県庁 (3)参加者:各府県教育長 (4)内 容:PDF版配布 3.データベース拡大及び発信事業 (1)時 期:通年 (2)場 所:各事務所 (3)内 容:英文、中文で訳した脳脊髄液減少症データベースページを発信 4.シンポジウム準備会議 (1)時 期:通年 (2)場 所:議員会館等 (3)参加者:厚労省、国土交通省、文部科学省 (4)内 容:脳脊髄液減少症ページの充実等 文章作成(2015.9.20) 文章改定(2018.10.14) 文章改定(2021.10.21) 文章改定(2022.10.26) 文章改定(2022.10.17) |
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
2023年度版
小児・若年者の脳脊髄液減少症患者から自殺者が出ました。相談窓口やその他対策ができないかと考えた結果、自殺対策基本法の骨子をまとめた、NPOライフリンク清水氏と懇談しアドバイスを得て、厚労省が開催する知事や首長が出席する地方トップ会議にも出席し、今後検討していきます。 また黒岩神奈川県知事と8月31日県知事室で面談、今後神奈川県では小児・若年者の不登校性の調査、脳脊髄液減少症の啓発を実施していく事になった(各県のモデルになるでしょう) 2023年度 広島県尾道市と連携し市民公開講座(シンポジウム)を2024年3月10日開催します。 現在、中井が頻繁に尾道市と交渉既に市長からメッセージを受け取っている。 https://youtu.be/vJKdwNyrSNI このシンポジウムではZOOMによる500名限度の無料公開となる予定です。 また石川県とも連携し2023年11月12日 脳脊髄液減少症勉強会を実施します。 この勉強会会場予算は県が負担、今年、高度専門医療人材養成事業費に脳脊髄液減少症の専門医を育てる事に100万円計上、この費用から捻出される、また金沢大学脳神経外科協力のもと、県内著名脳外科医5名を選出金沢脳脊髄液漏出症研究会を設立、第一回目の会議に中井も参加、今後石川モデルとして広まっていくだろう。 一般社団法人日本脳脊髄液漏出症学会(2023設立)と連携をしています。 小児の患者・交通事故の患者・新型コロナ後遺症患者等の症例登録が必須になると考えています。 ニュースより、東京都内のクリニックの後遺症外来では、8月以降、患者が急増し、先月はおよそ1800人が受診しました。最新の報告では、感染者の4人に1人が半年後も倦怠(けんたい)感や嗅覚障害などの症状が続くとしていますが、現在も治療法は確立されていません。 11カ月間後遺症に苦しむ女子大学生(19):「特に嗅覚のことは片っ端からサイトを見てちょっと一喜一憂したりとか、調べても『治らない人がいる』とか出てきちゃう。つらいのでいい治療が出たらいいなと思う」ANNの取材で、厚労省が初めて後遺症に特化した「診療の手引き」を作成し、今月中にもホームページ上で公表することが分かりました。 この診療の手引きの中には脳脊髄液減少症の事が書かれていないと推測します。 後遺症に悩む患者症候群と脳脊髄液減少症の患者の症状がほぼ一致、髄液漏れでなく、髄液産生低下のせいではと専門医は語る、この辺を共同研究しなければなりません。 毎年地域の脳脊髄液減少症の患者会と連携し、特に地域に専門医が少ない所を対象に、専門医、中井が講演シンポジウムを行なっています。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
1)日中(日本ー中国)脳脊髄液減少症研究会発足。 浙江大学医学部麻酔科と脳脊髄液減少症について様々な点から研究その他で協力する事になりました。
更に中国の本疾患の中心的役割を果たしています、浙江大学医学部より、中井に対して浙江大学医学部疼痛センター 脳脊髄液減少症マネージメントセンター客員教授の任命があり、中国での脳脊髄液減少症の普及活動のアドバイスをいただいています。今後も連携を計っていきたいと思います。 2022年、浙江大学医学部より連絡が入り、中井の浙江大学医学部疼痛センター 脳脊髄液減少症マネージメントセンター客員教授の任期が2025年までの3年延長となりました。 |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
2023年度
1)国(省庁)との連携は当会の目玉でもあります、地方行政との連携は47都道府県とは実施中で ありさらに 47都道府県議会局とも連携が密であります。 2024年度診療報酬引上げの為、厚労省医療課と面談し会議をおこない、最終、ブラッドパッチ療法が本来あるべき適正な評価を得て現状の点数800点から引き上げられるか注目されている。 本来医療費の総得点は決まっているため、優先順位の高い所から(中位協議連絡会)で審議され点数が決まっていく制度となっている。よって優先順位の高い項目の内、国民からの注目度も評価の対象となる、当会では患者さまに地方行政議会局に対し、「ラッドパッチ療法が本来あるべき適正な評価を得る地方議会から国へあげる意見書99条を採択するような」活動をお願いし現在 20道府県議会50市議会等で採択されている 詳細はこちら http://www.npo-aswp.org/ikensyo.html 当然地方からの声は国に届くので無視はできなくなる。 さらに一番頭を悩ますのが自賠責保険等の事故被害者の事故と脳脊髄液減少症の因果関係や後遺症が出た場合の診断を 「いつ どこで だれが どのように」おこなっているのかがまったくブラックボックス内で実施されている。 労災ではほぼ開示できるのですが、公正公平とは程遠い内容で、自賠責保険の場合 営利団体と密接の関係にある医師団が診断していると思われます、と同時にこの疾患は国が数億の予算を計上し13年間の研究で存在を認めた病態で保険適用の対象となっている、管轄部署の国土交通省も税金を使用し啓発に乗り出している、であるが事故後、この病気を疑い損保会社自賠責担当者にこの病気かもしれないので治療を受けたいと述べた瞬間から支払いを打ち切られるケースが後を絶たない、その理由は現在わかっているが、内部資料の為、公開できないのである。よってこの件を金融庁に相談したところ「データが欲しいとのこと、自賠責不払い調査フォーマットを金融庁の指導の元作成」 現状16名の方々が被害にあっている。http://www.npo-aswp.org/catego5-06.html 信じがたい事実ですがこれが現実なのです。将来的には被害に遭った方々の弁護団が必要かもしれません。 2)行政公式HPに脳脊髄液減少症のページを作成してもらい、本事業の目玉であるデータベースページへのリンクをそれぞれ、日本財団のロゴ入りバナーを貼り付ける事業で共同作業をおこなっています。既に47都道府県達成 (2018年10月1日現在) http://csf-japan.org/japanese/link.html 一つの疾患をテーマに行政が単独のページを作成し、そこに財団ロゴマーク入りのバナーを貼り付ける事は稀と考えられます。 更に厚労省との直接リンク https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nanbyo/100402-1.html 文部科学省との間接リンク http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353640.htm 国土交通省との間接リンク http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/other/data.html 金融庁との連携 http://www.npo-aswp.org/catego5-06.html |
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
1月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 会費 |
|
|
|
| 寄付金 |
|
|
|
|
| 民間助成金 |
|
|
|
|
| 公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| その他収入 |
|
|
|
|
| 当期収入合計 |
|
|
|
|
| 前期繰越金 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 |
| 当期支出合計 |
|
|
|
| 内人件費 |
|
|
|
| 次期繰越金 |
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
|
|
|
|
| 受取民間助成金 |
|
|
|
|
| 受取公的補助金 |
|
|
|
|
| 自主事業収入 |
|
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
|
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
|
|
|
|
| 経常収益計 |
|
|
|
|
| <支出の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | 2026年度(当年度)予算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
|
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
|
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
総会 理事会で決定
|
会員種別/会費/数 |
正会員40名 賛助会員200名
団体賛助会員3団体 http://www.npo-aswp.org/catego3-04.html スポンサー賛助会員4名 http://www.npo-aswp.org/catego3-02.html プロフェッショナル賛助会員18件 http://www.npo-aswp.org/catego3-03.html 正会員1万円/年 賛助会員5000円/年 団体賛助 20万/年 スポンサー賛助3万/年 プロフェッショナル賛助 12万/年 |
加盟団体 |
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
2名
|
2名
|
| 非常勤 |
1名
|
1名
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
1名
|
1名
|
|
| 常勤職員数 |
4名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
6名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
20名
|
||
報告者氏名 |
中井 宏
|
報告者役職 |
代表理事
|
法人番号(法人マイナンバー) |
5170005001716
|
認定有無 |
認定あり
|
認定年月日 |
2016年3月29日
|
認定満了日 |
2026年3月28日
|
認定要件 |
絶対値基準
|
準拠している会計基準 |
NPO法人会計基準
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
実施済み
|
監視・監督情報 |
当会監査により経理状況監査実施
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2025年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2022年度
|
|||
|
2021年度
|
|||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2026年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2025年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















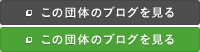
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する