|
IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所](任意団体)
|
団体ID |
1502420258
|
法人の種類 |
任意団体
|
団体名(法人名称) |
IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]
|
団体名ふりがな |
ひととそしきとちきゅうのためのこくさいけんきゅうしょ あいあいえいちおーいー
|
情報開示レベル |
|
第三者認証マーク |
|
団体の概要 |
IIHOEは
Keep It Simple and Sharp! (目標も組織も簡潔で鋭く) Needs Driven! (そのテーマ・事業は社会に求められているか?) Listen! and Respond.(まずしっかり聞く。聞いたら、見捨てない) Unique & Astonishing! (私たちらしく、成果は世界的にスゴイか?) Buck stops here」!(引き受けたら、徹底的にやりきる) という、運営上の原則を大切にしています。 IIHOEは、場所を持たずに、場を設けることに特化したNPOです。本当に社会を変えるには、自分たちが大きくなるのではなく、既に活動中の団体や、企業や行政が、より調和的で民主的な発展を実現できるよう支援することが大切であり、自らの規模は小さく保ち、最も大きな社会的なインパクトを与えられるよう心がけています。 このため、私たちの事業のほとんどは、他団体や企業・行政機関との協働によって始まり、社会の変化に応じて、継続する方法も進化させています。 また、「1歩先の視野を持ち、半歩先のプログラムをつくる」NPOを支援する者として、「2歩先の視野を持ち、1.5歩先のプログラムをNPOや企業・行政に提案する」ことが、私たちの基本的な役割です。さらに、自らモデルとして動き出すこともあります。 日本初(?)のNPOの運営に関する連続講座(1995年)や、世界初(?)のNPO運営専門誌の創刊(99年)、事業系NPOのリーダーが分野を超えて学び合う場づくり(2000年)、自治体の「協働しやすさ」を可視化した世界初の「協働環境調査」(04年~14年)など、次の社会づくりに求められる事業を生み続けています。さらに、社会を変えようとする者は、NPOなどの組織運営のみならず社会を運営する視点で取り組んで欲しいという思いから、「ソシオ・マネジメント」を創刊(14年~)し、「ソシオ・マネジメントスクール」を開校(15年)しています。 また、年次報告書を通じて、積極的に情報開示しています。ぜひ団体ウェブサイト(http://blog.canpan.info/iihoe/)からご覧ください。 |
代表者役職 |
代表者
|
代表者氏名 |
川北 秀人
|
代表者氏名ふりがな |
かわきた ひでと
|
代表者兼職 |
「ソシオ・マネジメント」編集発行人
|
主たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
104-0033
|
都道府県 |
東京都
|
|
市区町村 |
中央区
|
|
市区町村ふりがな |
ちゅうおうく
|
|
詳細住所 |
新川1-6-6
|
|
詳細住所ふりがな |
しんかわ
|
|
お問い合わせ用メールアドレス |
office.iihoe@gmail.com
|
|
電話番号
|
電話番号 |
03-6280-5944
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金
|
|
備考 |
|
|
FAX番号 |
FAX番号 |
03-6280-5945
|
連絡先区分 |
事務所・勤務先
|
|
連絡可能時間 |
10時00分~18時00分
|
|
連絡可能曜日 |
月 火 水 木 金 土 日
|
|
備考 |
|
|
従たる事業所の所在地 |
郵便番号 |
|
都道府県 |
|
|
市区町村 |
|
|
市区町村ふりがな |
|
|
詳細住所 |
|
|
詳細住所ふりがな |
|
|
URL |
団体ホームページ |
|
団体ブログ |
||
|
|
||
X(旧Twitter) |
|
|
代表者ホームページ(ブログ) |
||
寄付 |
|
|
ボランティア |
|
|
関連ページ |
||
閲覧書類 |
||
設立年月日 |
1994年8月25日
|
|
法人格取得年月日(法人設立登記年月日) |
|
|
活動地域 |
日本全国および海外
|
|
中心となる活動地域(県) |
東京都
|
|
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
|
役員数・職員数合計 |
2名
|
|
所轄官庁 |
|
|
所轄官庁局課名 |
|
|
活動分野 |
主たる活動分野 |
市民活動団体の支援
|
|
|
地域・まちづくり、環境・エコロジー、人権・平和、国際協力、経済活動の活性化、起業支援、助成活動、食・産業、漁業、林業、行政への改策提言
|
|
設立以来の主な活動実績 |
1994年:創設、「人・組織・地球」創刊(99年休刊)
95年:神戸で被災者のお手伝い(被災者情報支援センター:ICCDS設立)、NPOのマネジメント支援開始。有機農業分野の運動・事業展開等(99年まで)、「若いリーダーのためのマネジメント講座」開講 96年:「環境問題の基本構造」、「エコロジーとビジネス」開講 97年:地球環境基金や経団連自然保護基金のNPOマネジメント講座受託 99年:「NPOマネジメント」創刊(~2011年4月)、台湾中部地震の支援寄付呼びかけ、33万円提供 2000年:マネジメント関連研修が年100件超える。英語でも開始、『NPO理事の10の責任』など5冊の日本語版刊行、環境gooで「環境コミュニケーションの考え方・進め方」連載開始。世界初の「環境報告書リサーチ」とシンポジウムの企画・運営も開始 01年:中間支援組織スタッフ対象の研修開始。環境・社会レポートへの第三者意見執筆や市民との対話の企画・運営に着手 04年:「都道府県・主要市におけるNPOとの協働環境調査報告書」刊行(05・07・09年・14年にも実施)、ICCDSで新潟の水害・震災支援。 06年:「助成申請書・報告書の設問調査」実施 07年:「NPOの情報開示」と「地域企業のCSR」の勉強会を各地NPO支援センターと協働開催、「社会事業家マネジメント塾」「ステークホルダー・エンゲージメント塾」開講 08年:「地域・テーマ公益ポータル推進プロジェクト」開始 09年:「団体基本情報に関する地域規模・全国規模助成の比較調査報告書」刊行 10年:「社会的責任に関する円卓会議」で「持続可能な地域づくりワーキング・グループ」を運営、せんだい・みやぎ、きょうと、岡山の各NPOセンターと「支援人材合同育成プロジェクト」発足 11年:「被災者をNPOとつないで支える合同プロジェクト」(つなプロ)設立、幹事団体就任 12年:「自治体における社会責任(SR)への取り組み調査」実施(調査実施を(一財)ダイバーシティ研究所に委託)、代表川北が(公財)日本財団 次の災害に備える企画実行委員会代表委員に就任 13年:「自治体における社会責任(LGSR)への取り組み調査」を刊行、全国11か所で報告会開催 14年:「ソシオ・マネジメント」(SMR)創刊号刊行、第5回「都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査」実施、14年度内に7カ所で報告会開催。 15年:「ソシオ・マネジメント・スクール」(SSM)開校。ICCDSでネパール震災、関東・東北水害支援。 16年:「フロンティア・サイト・ヴィジット」スタート、SMR第3号刊行、ICCDSで熊本地震被災者支援 17年:SMR第4号・第5号刊行、「成果を最適化するための助成プログラムのコミュニケーション調査」実施、SSM6コース継続開催 18年:SMR第6号刊行、SSM予科と特別講座「桜井番頭塾」開催、「NPO/NGOにおけるスタッフの働き方の多様性に対応した組織マネジメント」に関する調査および報告会実施 19年:創設25周年謝恩プログラム「25+」を全国13団体のご協力で23回開催、SMR第7号・第8号刊行 20年:SMR第9号~第11号刊行、ネットストアにて書籍販売開始。 ※入力文字数上限のため、21年以降は年次報告書をご参照ください。 |
|
団体の目的
|
地球上のすべての生命にとって、民主的で調和的な発展のために
|
|
団体の活動・業務
|
1.社会事業家のマネジメント支援
○講座・研修(95年開講。2000年から20年連続で年間100件以上) 主なテーマは「小規模多機能自治」、「しくみづくりの意義と手法」、「人材・組織を育てる」、「目的・目標の定義」、「計画の基礎」など。 「社会事業家100人インタビュー」((一社)ソーシャルビジネス・ネットワークとの共催、12年~) 「ソシオ・マネジメント・スクール」(15年~) 「フロンティア・サイト・ヴィジット」(国内の先駆的な取り組みを、課題に挑む人々とともに訪ねる。16年~) 「雲南市に地域自治を学ぶ会」(雲南ゼミ) ○個別カウンセリング ○隔月刊誌「NPOマネジメント」編集・発行(99年創刊、11年4月に終刊) ○「ソシオ・マネジメント」編集・発行(12年~) ○NPOのマネジメントに関する書籍の翻訳・発行 ○NPOと企業・行政との協働の推進 協働を育てるための市民・行政の合同研修の企画・運営 報告書「都道府県・主要市におけるNPOとの協働環境調査」(04年、05年、07年、09年、14年) 自治体における「社会責任」(SR)への取り組み調査(13年) ○NPO支援組織の戦略支援 NPO支援センターのスタッフ育成 助成プログラムの戦略・運営支援 ○団体の情報開示と、助成プログラムの最適化の支援(GATEプロジェクト) NPOと助成機関とのコミュニケーション不全の解消に向けた調査・提言・支援 助成機関の審査精度と事務効率の向上に向けた調査・提言・支援 ○企業の製品やサービスの割引・提供プログラムの開発 2.ビジネスと市民生活を通じた環境問題・社会的課題の解決 ○企業の社会責任・貢献戦略のデザイン(第三者意見執筆 通算延べ157件) ○市民と企業との対話の支援(ダイアログの企画・運営 延べ100件) ○環境gooにて「環境・社会コミュニケーションの考え方・進め方」(2000~15年連載、第184回にて終了) 3.2030年の地球への行動計画立案 |
|
現在特に力を入れていること |
【国際交流・多文化共生、NPOにおけるハラスメント予防と対応に関する、セミナーや担い手育成】
(公財)かめのり財団のご高配により、連続オンラインセミナー「国際交流の新局面」「多文化共生の転換点」に加えて、「かめのり多文化共生塾」の企画・運営に協力。概要は同財団ウェブサイトに掲載されています。また、中小企業を含む全事業者で義務化されたハラスメント対応について、雇用関係以外でもハラスメントのリスクがあるNPO/NGOにおけるハラスメントの予防や対策についての団体内での体制整備を目的に、一次対応の「訓練」なども行っています。 【草の根からの民主主義を実践する「小規模多機能自治」を促す】 島根県雲南市でのお取り組みを「小規模多機能自治」と名付け、発足直後の06年からお手伝いさせていただき、地域自治力の重要性と福祉・経済・健康への効果の大きさを共有するために「雲南市に地域自治を学ぶ会」(雲南ゼミ)を13年に発足。全国からのご参加者とともに学ばせていただく機会は、24年度は5年ぶりに再開され、累計16回、延べ参加者数200名超となりました。 15年2月発足の「小規模多機能自治推進ネットワーク会議」の自治体会員も増え続け、278(2県220市53町3村)と、全市町村の6分の1に。5月には「初任者研修」をオンラインで、10月には「小規模多機能自治のつどい」と支援者実務研修を東京で開催しました。 【より良い社会づくりを効果的に導くための、助成プログラムの支援】 現在、川北が選考・運営・評価に携わる助成事業は、官民計12件にのぼります。 このうち、科学技術振興機構(JST)の社会技術研究開発センター(RISTEX)の複数の領域において、アドバイザーや総括として、研究成果を社会に実装・定着する支援を08年から行っています。 【市民活動支援施設・組織のスタッフと組織を育てる】 IIHOEでは設立直後から、支援スタッフ・役員を対象とした「支援力研修」を主催し続けています。24年度は主催としては開催できませんでしたが、中国5県中間支援組織連絡協議会主催による岡山と鳥取で開催された各種のプログラムを共催しました。 |
|
今後の活動の方向性・ビジョン |
<25年度の方針>
24年までに取り組んだすべてのテーマについて、さらに深く広く働きかけます。重点的なテーマは、以下の5つです。 (1)まっとうな社会事業家・社会起業家の「事業経営力」「ガバナンス力」育成とコミュニティ形成 「社会を変える」ことより、「変わってしまった社会に、心を(心で)補う」ことが大切な今。社会起業家やその支援者を標榜する団体の過剰供給下であることから、SBNなどと協働して、日本を代表する社会事業家のビジネスモデルを明らかにする「社会事業家100人インタビュー」や、「ソーシャルビジネス白書」により実態と意欲の把握を進めるとともに、「理事会と理事を生かし育てる研修」などの実施を通じて、まっとうな社会事業家による「まっとうな事業と組織運営の基盤づくり」を加速しコミュニティ形成を促します。 (2)まっとうな協働・総働を促すための研修と基盤づくり 市民と行政がともに地域を耕すために不可欠なプロセスである協働・総働を促す研修に従来通り協力するとともに、2030年代を視野に入れた協働・総働の在り方と、その実現に向けた工程を示せるよう、基盤づくりを進めます。 (3)地域の総力を挙げた「総働」による「持続可能な地域づくり」と「地域経営」の推進 農山漁村部のみならず、今後は東京をはじめとする都市部においても加速度的に進む多老化、人口減少、そして「小家族化」に直面する地域において、企業や学校なども含め、総力を挙げた「総働」(マルチ・ステークホルダー・プロセス)を通じた「持続可能な地域づくり」を適切に進め、課題先進国から課題解決先駆国へと転換するために、「小規模多機能自治」を体系的に学び、全国に拡げる場を、各地の方々とともに設けるとともに、先行した地域における「地域経営」の基盤づくりに取り組みます。 (4)中間支援組織・助成機関の支援と、「地域づくり」支援に向けた人材育成基盤づくり 期待に適う役割を果たせていない市民活動支援センターや、戦略の再構築が求められる助成機関を対象に、管理職級職員や理事など、業務や組織の管理・運営にあたる人材を育てるために、SMR第10号「支援・評価・助成の基礎と戦略」をテキストとした研修を引き続き開講し、その修了者などのコミュニティづくりを働きかけます。 (5)「ソシオ・マネジメント」をはじめとする書籍の刊行・販売 手元在庫を最大限に活用し、テキストとして対面・オンライン研修を順次開催します。 |
|
定期刊行物 |
『NPOマネジメント』の続編となる『ソシオ・マネジメント』を発行。
・創刊準備号(12年6月発行)「社会事業家は、どう育つか、どう育てるか」(品切) http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/205 ・創刊号(14年7月発行)「社会に挑む5つの原則、組織を育てる12のチカラ」 http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/217 ・第2号(15年2月発行)「社会事業家100人インタビュー 前編」 http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/220 ・第3号(16年4月発行)「小規模多機能自治-総働で、人「交」密度を高める」 http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/222 ・第4号(17年6月発行)「成果を最適化するための助成プログラムのコミュニケーション調査」 http://blog.canpan.info/iihoe/archive/361 ・第5号(17年6月発行)「ベスト・プラクティスから学ぶCSRマネジメント」 http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/226 ・第6号(18年6月発行)続・小規模多機能自治「地域経営を始める・進める・育てる88のアクション」 http://blog.canpan.info/npomanagement/archive/229 ・第7号(19年9月発行)ソーシャルビジネス白書 第0号「ソーシャルビジネスの『これまで』と『これから』」 https://blog.canpan.info/npomanagement/archive/235 ・第8号(19年12月発行)「社会事業家100人インタビュー 中編」 https://blog.canpan.info/npomanagement/archive/236 ・第9号「社会に挑む組織のガバナンス」 https://blog.canpan.info/npomanagement/archive/243 ・第10号「支援・評価・助成の、基礎と戦略」 https://blog.canpan.info/npomanagement/archive/244 ・第11号「世界初の「超々」高齢都市へ 2030年代の東京に、どう備えるか?ーデータでみる東京の『これまで』と『これから』」 https://blog.canpan.info/npomanagement/archive/248 『NPOマネジメント』(99年創刊、11年4月終刊) (全記事のリストはhttp://blog.canpan.info/npomanagement/category_3/ 参照)。 |
|
団体の備考 |
IIHOEは、任意団体です。
代表者の川北は、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)の制定当時、既に活動中のNPOの一員として、また、国会議員の政策担当スタッフとして、制定過程にもかかわりましたが、IIHOEでは特定非営利活動法人(通称:NPO法人)の認証を受けずに、任意団体のままで活動を続けています。その理由は、「法人認証を受けなくても、NPOとして活動を続ける上で、まったく支障がない」ということに尽きます。 法人認証を受ける「メリット」としてよく挙げられるのは、「社会的な認知が高まる」「契約の主体になれる」といったものですが、94年に設立し、95年から本格的な活動を開始したIIHOEにとって、同法施行(98年)当時、すでにわずかながらの実績を積極的に情報開示することで、他のNPOや行政機関・企業と連携したり、ご依頼をいただいたり、といったことが実現できていました。 もちろん、介護保険事業などのように、事業者認可や契約に法人格が必要とされているものもありますが、一般的に、行政や企業との契約は、任意団体でもなんら支障がありません。大切なのは、「任せて大丈夫か?」という不安に応える実績や情報開示こそが重要であることは、相手側の立場から見ればおわかりいただけると思います。 また、法人認証を避けてきた積極的な理由もありますが、詳しくは(http://blog.canpan.info/iihoe/archive/8)をご参照ください。 もちろん、同法は市民社会を拡充する上で重要な役割を果たしており、IIHOEはこれからも、その適切な運営や改善に協力します。 |
|
助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 |
なし(NPOや企業・行政を「支援」するプロフェッショナルとして、支援は自分たちが受けるのではなく、現場で活動する団体が受ける支援をよりよいものにするのが自分たちの役割であると考え、設立以来、助成・補助は受けていません)。
|
他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 |
・神奈川県と、同県内の11のNPO支援団体・センターとともに、神奈川福祉事業協会の協力を得て「かながわNPOマネジメント・カレッジ」を開催し、計1000人以上が受講(01年~03年)。
・全米NPO理事センター(NCNB、現BoardSource)の『理事を育てる9つのステップ』『ボランティア・マネジメントと理事会の役割』『NPO理事による事務局長評価』『NPO理事会の自己評価』の日本語版を、(社福)大阪ボランティア協会、(特)市民フォーラム21・NPOセンター、(特)せんだい・みやぎNPOセンター、東京ボランティア・市民活動センター、(特)長野県NPOセンター、(特)ひろしまNPOセンターの協力を得て刊行・販売(00年)。 ・各自治体の「協働しやすさ」の整備状況と課題を可視化する「都道府県・主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査」と、その報告会を、全国各地のNPO支援センターのご協力を得て実施。第2回(05年)は210自治体について、26のセンターと協働調査し、報告会を18か所で開催。第3回(07年)は252自治体について、33のセンターと協働調査し、報告会を19か所で開催。第4回(09年)は183県市について、29のセンターと協働調査し、報告会を16か所で開催。第5回(14年)は調査統括を(特)岡山NPOセンターに委託し、255県市について、36のセンターと協働調査し、報告会を23か所で開催。 ・全国14のNPO支援センターのご協力を得て、各地の自治体とNPOとの協働事業23件のポイントをまとめた「協働事例集」を、「NPOマネジメント」第51号から第54号に連載。 ・NPO支援センターやボランティアセンターなど、中間支援組織のスタッフ対象の「支援力をつける!パワーアップ研修」について、(特)きょうとNPOセンター、(特)宝塚NPOセンター、(特)せんだい・みやぎNPOセンター、おきなわ市民活動支援会議などご当地のNPO支援センターに、企画・運営にご協力いただいて開催(01年~)。 2012年からは岡山NPOセンターをはじめとする中国5県中間支援組織協議会のご協力をいただき、合同で人材育成をする機会として「地域力・協働力・支援力研修」を中国地方で開催。 ・より積極的な情報開示を通じて、NPOがより多くの市民・企業・行政から信頼と支援を受けられるための基盤としての、地域ごと・分野ごとの団体・活動情報のデータベースやポータルサイトの整備を促す「地域・テーマ公益ポータル推進プロジェクト」を、全国18のNPO支援組織と、日本財団(CANPAN)との協働で実施(08年~)。 ・(特)せんだい・みやぎNPOセンター、(特)きょうとNPOセンター、(特)岡山NPOセンターの3センター合同でマネジャー級スタッフを育成するために「支援人材合同育成プロジェクト」を発足。年に3回程度、各団体の所在地を訪れながら、テーマ別研究や組織基盤分析などを実施(10年~11年)。 ・NPOのSR課題に本気で取り組み、共に解決しようと、IIHOEと(一財)ダイバーシティ研究所のよびかけのもと、2012年9月より、NPOのSR取組を推進するための研究会を実施。17年度は13団体にご参加(うち3団体はオブザーブ)いただき、各組織の取り組みや課題の共有(ピアレビュー)や勉強会を開催中。 ・2013年に都道府県・政令指定市・県庁所在地市(計98自治体)を対象にした「自治体における『社会責任』(LGSR)への取り組み調査」を実施((一財)ダイバーシティ研究所に委託)し、その報告会を、各地の中間支援機関のみなさまにご協力いただき、東京・大阪・防府(山口県)・広島・名古屋・京都・岡山・静岡・函館・千葉・新潟の計11か所で開催。 ・2017年8月に、日本財団CANPANプロジェクトとの協働により、NPO対象の助成プログラムの決定事業一覧(通称:ホワイトリスト)のパイロット版を公開。全国規模で募集され、助成先事業の一覧を公開している助成プログラムについて、その助成先事業を一つの表計算ファイルにまとめ、「どの助成機関がどの団体のどんな事業にいくら助成したか」だけでなく、「どの団体が各助成機関から、合わせていくら助成を受けたか」という、逆引き検索もできるように設定。 ・2018年は「ソシオ・マネジメント・スクール」を、中国5県中間支援組織連絡協議会のご協力により「先駆的なしくみ事例から学ぶ協働推進戦略の基礎」、「各地の事例から学ぶ小規模多機能自治推進施策の基礎」を岡山で開講するとともに、「小さな組織の番頭論」を著された日本一の番頭・桜井義維英さんを塾頭に迎えた特別講座を、川崎市青少年の家と同講座実行委員会との共催で開講。 ・2019年は、設立 25 年謝恩プログラム「25+」(twenty-five_and_beyond)を23回開催。開催にあたり、全国の中間支援組織等20団体にご協力いただきました(組織名は19年の年次報告書表2参照)。また、18年に引き続き、桜井義維英さんを塾頭に迎えた特別講座を、川崎市青少年の家と同講座実行委員会との共催で開講。 ・2020年は、非営利組織評価センターとの共催で、SMR第10号「支援・評価・助成の基礎と戦略」を教材とした3回連続オンライン研修を2シリーズ開講。 ・21年は日本アウトドア・ネットワーク(JON)の協力を得て、ひとり親世帯のこどもたちの自然体験活動参加を支援する助成制度を設立。また、NNネット、NSRプロジェクト、事務支援カンファレンス、非営利組織評価センターによる「非営利セクターのガバナンス拡充プロジェクト」を構成し、現状把握調査実施。 ※入力文字数上限のため、以降は年次報告書をご参照ください。 |
企業・団体との協働・共同研究の実績 |
・サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク(NSC)、環境goo(現:緑のgoo)を運営するNTTレゾナントとの協働で、環境報告書やCSRレポートの読者に対する世界初の体系的な調査である「環境・社会報告書読者調査」の設計・分析・発信を、創設段階から実施、協力しました(00年から14年)。
・(財)地球産業文化研究所の委託研究の報告書として「NPOと企業・行政とのより深い協働をめざして」刊行(04年)。 ・(独法)科学技術振興機構 社会技術研究開発センター(RISTEX)SDGsの達成に向けた共創 的研究開発プログラム(SOLVE for SDGs)総括就任(19年から総括補佐)。 ・国際協力機構(JICA)によるマリ国別研修 持続的発展のための地方行政強化コースに協力(23年・24年)。 本欄の趣旨とは異なりますが、企業の社会責任(CSR)への取り組みを促進するため、(1)各社の環境報告書・CSRレポートへの第三者意見執筆、(2)市民との対話(ステークホルダー・ダイアログ)の企画・運営、(3)役職員対象の研修を通じて、各企業にお手伝いしています。 【24年の主な実績】 企業の社会責任への取り組みに市民の立場から包括的に意見を述べる「第三者意見」を、SOMPOホールディングス(旧・安田火災から24年連続)、デンソー(21年連続)、カシオ計算機(18年連続)の計3社に執筆。 |
行政との協働(委託事業など)の実績 |
本欄の趣旨とは異なりますが、自治体職員やNPO、地縁組織が協働を学ぶ研修をお手伝いしています。
【最近の主な自治体職員向け研修実績】 *地元のNPO支援センターと自治体の共催を含む。 *NPO・市民との合同研修を含む。 *カッコ内の数字は、実施年。例:(13・15)=2013年と2015年に実施。 北海道旭川市(11)、江別市(11)、士別市(13・14)、富良野市(06)、石狩市(09)、北見市(13・23・24)、登別市(13)、函館市(16)、下川町(15)、幌延町(23)、青森県(20・21)、八戸市(16)、中泊町(22・23)、岩手県(08・09・10・17)、盛岡市(09)、北上市(24)、久慈地方振興局(09)、県北広域振興局(10)、秋田県(11)、横手市(11・12・16)、美郷町(12)、平鹿地域振興局(11)、宮城県(20)、仙台市(11)、多賀城市(09)、石巻市(13・17)、東松島市(16)、気仙沼市(17・18)、角田市(17)、丸森町(17)、山形県(17・18・23)、山形県職員育成センター(06~24)、新庄市(17・18)、寒河江市(18)、鶴岡市(18)、最上総合支庁(13・15)、庄内総合支庁(18)、庄内町(23・24)、福島県(06)、長野市(20)、茨城県龍ケ崎市(16)、稲敷市(17)、千葉県(08・13・15・21・23)、白井市(21~24)、佐倉市(06)、浦安市(09)、勝浦市(15)、四街道市(13)、富里市(17)、酒々井町(12・16)、埼玉県戸田市(15)、東京都八王子市(06・11)、府中市(14)、神奈川県(11)、神奈川県自治総合研究センター(06~08)、横浜市(12)、平塚市(13)、静岡県(23)、浜松市(17)、袋井市(22)、静岡市(17~24)、富士市(20・21・23)、磐田市(20・21)、裾野市(24)、新潟県(07・10・16)、魚沼市(22)、新潟市(10・11・15)、糸魚川市(14)、燕市(15)、妙高市(15)、阿賀野市(16)、富山県(09)、富山市(14)、小矢部市(09)、南砺市(16・20)、石川県氷見市(15・16)、七尾市(16)、白山市(23・24)、羽咋市(24)、福井県大野市(24)、長野県松本市(12)、高森町(15)、群馬県富岡市(22~24)、山梨県(09)、笛吹市(09)、愛知県三好町(06~09)、安城市(22)、豊田市(06・19・20)、小牧市(13・16)、東海市(13)、江南市(16)、大口町(17)、設楽町(18)、滋賀県東近江市(20・23)、竜王町(21)、日野町(22)、三重県(11・12~13)、名張市(16)、伊賀市(16)、甲賀市(20)、岐阜県関市(13・16・20)、美濃加茂市(24)、高山市(21)、松阪市(15)、鈴鹿市(16)、中津川市(16)、京都府京丹後市(17)、京田辺市(24)、奈良県(08)、奈良市(12・13・20)、大阪府岸和田市(15)、堺市(10・12)、高石市(24)、八尾市(13)、河内長野市(13)、阪南市(16・17・22)、大阪市(18・20・21・23)、東淀川区(21・22)、和歌山県田辺市(20・21)、兵庫県尼崎市(15)、豊岡市(15・16)、伊丹市(16)、丹波市(17)、朝来市(18)、鳥取県(08~10・13)、岩美町(18)、島根県(07~10・12~14)、松江市(12~18)、雲南市(11・12・16~18・21・24)、江津市(13~16)、浜田市(15)、益田市(13)、吉賀町(07)、岡山県(13)、赤磐市(14)、瀬戸内市(11)、笠岡市(06)、岡山市(12・13・16・18)、備前県民局(06・09・10・12・14)、美作県民局(07・08・16)、総社市(09・13)、備前市(15)、倉敷市(16)、美咲町(13)、津山市(16・17)、広島県三原市(08~10・12)、竹原市(11)、尾道市(12~15)、廿日市市(12~14・18・22)、庄原市(13・14・16)、東広島市(23)、世羅町(17)、山口県岩国市(11・15)、長門市(23)、宇部市(14・16)、下関市(07~09)、周南市(15・17)、防府市(07・08・10・13)、光市(12)、徳島県自治研修センター(07・08)、愛媛県(12)、高松市(07~11)、西予市(09)、高知県須崎市(15・16)、高知市(22~24)、福岡県(07・09・13)、宗像市(21~23)、北九州市(08・11)、筑後市(16)、佐賀県(07~12)、佐賀市(06・10・17)、小城市(08・13・14)、唐津市(08)、嬉野市(12)、武雄市(13)、長崎県(07・13~15)、長崎市(10・11・13・14・16~24)、佐世保市(07・08)、平戸市(14)、五島市(17・18)、大分県(06・07・10)、杵築市(15・24)、佐伯市(07)、別府市(14~16)、日田市(16)、宮崎県(06・07・11)、都城市(10)、鹿児島県(14)、沖縄県(21)、那覇市(08・10)、宜野湾市(16) |
最新決算総額 |
1,000万円~5,000万円未満
|
会計年度開始月 |
1月
|
その他事業の有無 |
無
|
 CANPAN標準書式で表示しています。
CANPAN標準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 会費 |
0円
|
0円
|
|
| 寄付金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 民間助成金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 公的補助金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 自主事業収入 |
37,023,243円
|
33,780,365円
|
|
|
| 委託事業収入 |
0円
|
0円
|
|
|
| その他収入 |
9,870円
|
125,724円
|
|
|
| 当期収入合計 |
37,033,113円
|
33,906,089円
|
|
|
| 前期繰越金 |
77,668,795円
|
78,826,986円
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 |
| 当期支出合計 |
36,089,887円
|
36,213,600円
|
|
| 内人件費 |
16,560,000円
|
16,560,000円
|
|
| 次期繰越金 |
78,826,986円
|
76,895,956円
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産 |
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 資産の部合計 |
|
|
|
| <負債の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債 |
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 負債の部合計 |
|
|
|
| <正味財産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 |
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
| 当期正味財産合計 |
|
|
|
 NPO法人会計基準書式で表示しています。
NPO法人会計基準書式で表示しています。
収支報告
| <収入の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 受取会費 |
0円
|
0円
|
|
| 受取寄附金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 受取民間助成金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 受取公的補助金 |
0円
|
0円
|
|
|
| 自主事業収入 |
37,023,243円
|
33,780,365円
|
|
|
| (うち介護事業収益) |
|
|
|
|
| 委託事業収入 |
0円
|
0円
|
|
|
| (うち公益受託収益) |
|
|
|
|
| その他収益 |
9,870円
|
125,724円
|
|
|
| 経常収益計 |
37,033,113円
|
33,906,089円
|
|
|
| <支出の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | 2025年度(前年度)決算 | |
| 内訳 | 事業費 |
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 管理費 |
|
|
|
|
| (うち人件費) |
|
|
|
|
| 経常費用計 |
36,089,887円
|
36,213,600円
|
|
|
| 当期経常増減額 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
|
|
|
|
| 経理区分振替額 |
|
|
|
|
| 当期正味財産増減額 |
|
|
|
|
| 前期繰越正味財産額 |
77,668,795円
|
78,826,986円
|
|
|
| 次期繰越正味財産額 |
78,826,986円
|
76,895,956円
|
|
|
| 備考 |
|
|
|
|
貸借対照表
| <資産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動資産合計 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
|
|
| 資産合計 |
|
|
|
| <負債及び正味財産の部> | 2023年度(前々々年度)決算 | 2024年度(前々年度)決算 | |
| 内訳 | 流動負債合計 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
|
|
| 負債合計 |
|
|
|
| 正味財産合計 |
|
|
|
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
|
意志決定機構 |
常勤スタッフによる運営会議。
|
会員種別/会費/数 |
|
加盟団体 |
社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク(NNネット)
|
役員・職員内訳 |
役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 |
1名
|
1名
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 無給 | 常勤 |
|
|
| 非常勤 |
|
|
|
| 常勤職員数 |
2名
|
||
| 役員数・職員数合計 |
2名
|
||
| イベント時などの臨時ボランティア数 |
|
||
報告者氏名 |
|
報告者役職 |
|
法人番号(法人マイナンバー) |
|
認定有無 |
認定なし
|
認定年月日 |
|
認定満了日 |
|
認定要件 |
|
準拠している会計基準 |
|
準拠している会計基準がその他の場合の会計基準名 |
|
監査の実施 |
未実施
|
監視・監督情報 |
|
定款・会則 |
|
最新役員名簿 |
|
パンフレット |
|
入会申込書 |
|
退会申込書 |
|
会員情報変更届 |
|
研究費・助成金申請書 |
|
その他事業に関する資料 |
|
決算・事業報告
| 決算報告書 (活動計算書/収支計算書) |
決算報告書(貸借対照表) | 決算報告書(財産目録) | 事業報告書 |
|
2025年度(前年度)
|
|||
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|||
|
|
|
||
|
2023年度(前々々年度)
|
|||
|
|
|
||
|
2022年度
|
|||
|
|
|
||
|
2021年度
|
|||
|
|
|
||
予算・事業計画
| 予算書類 | 事業計画書 |
|
2026年度(当年度)
|
|
|
|
|
|
2025年度(前年度)
|
|
|
|
|
|
2024年度(前々年度)
|
|
|
|
|
|
2023年度(前々々年度)
|
|
|
|
|
|
2022年度
|
|
|
|
|
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Reader のダウンロードはこちら















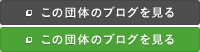
 過去5年分を表示する
過去5年分を表示する
 過去5年分の内訳を表示する
過去5年分の内訳を表示する