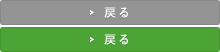事業成果物名 |
2023年度 親子みらいワーク~ライフワイドの視点で取りくむみんなのじりつの道しるべ~(重度障害者の自立支援プログラムの構築)
|
||||||||||||
団体名 |
|||||||||||||
事業成果物概要 |
事業成果物としての冊子
『親子みらいワーク~ライフワイドの視点で取りくむみんなのじりつの道しるべ~』(88頁) もくじ 1 発刊にあたって 2 寄稿 7 検討委員会メンバー紹介 8 作業部会メンバー紹介 9 事業のスケジュール表 青年期のライフワイド学習プログラム 13 学習プログラムの開発について 14 シュレオーテの紹介 15 レッツコネクトの紹介 16 学習プログラムの一覧表 17 学習要素の一覧表 18 学習プログラム(学びのネタ)+実践例(写真付き) 親のライフワイド学習プログラム 61 学習プログラムの開発について 62 学習プログラム全体の紹介 63 学習プログラムの準備方法 84 受講前後アンケート 86 ユーススコラ鹿児島 視察研修報告 88 編集後記 発刊にあたって 社会福祉法人いずみ野福祉会では2023年度から2024年度の2か年に渡り、日本財団の助成金を受けて『重度障害者の自立支援プログラムの構築』という事業に取り組みました。この事業の目的は“じりつ”をテーマにして、障害者本人を対象とした学びのプログラムと障害者の家族を対象にした学びのプログラムを開発することです。テーマである“じりつ”については、“自立”と“自律”という2つの表記を用いられることが多いですが、この事業では“じりつ”とひらがなで表記しています。ひらがなで表記する意図はこの課題を難しく考えすぎないようにしようということです。 “じりつ”を難しく考えがちになることには背景があります。一つ目の背景は、障害がある場合は親子の関係が密接になりがちで障害者本人が成人した後も子育ての延長戦がスタートしてしまって子離れのタイミングが見えづらい点です。親はわが子の障害を受け入れると同時に「この子を育てられるのは自分だけだ」という自負も生まれがちです。『子育て=唯一無二の親にだけできる介護』になってしまうと子育ての一段落が訪れることなく、主たる介護者としての生活が当たり前になってしまいます。 二つ目の背景は、入所施設やグループホーム、ひとり暮らしも含めた障害者の暮らしを支える制度が脆弱であることです。とくに重度の障害がある人については、親が安心してわが子の人生を託せる暮らしの場が見つからないという声が多数です。だから自宅で親子での生活が密着度を増しながら延々と続いてしまいます。その結果、老障介護という社会問題が生じています。 では、障害者のじりつを進めていくためにはどうすればいいのでしょうか?二つ目の背景に上げている暮らしの場の不足に関しては、入所施設やグループホームをはじめとした障害者福祉制度の発展が必要でありそれは国家予算にも関わる課題です。もし、この課題が前進して、入所施設には常に空床があり、グループホームにも希望すればすぐにでも入れる状態になれば老障介護は解決するのでしょうか? 実際にある事例として入所施設を希望していた人が、空きができたので入所できますよと声をかけられた時に、「うちはまだ大丈夫です」と断ってしまうことがあります。これは決して珍しいことではなく、入所を決意した場合も相当悩んで、一旦は見送ろうと思ったけどこの機会を逃していけないと決意したという話をよく聞きます。どうも“じりつ”に向けての心の準備が追いついていないのが実情であるようです。障害者にとっても、親にとっても“じりつ”という課題について、じっくりと考えたり、準備したり、体験したりする“学びの機会”があまりにも不足しているのでしょう。障害者とその家族に“じりつ”についての学びのプログラムが必要であるならば開発しようというのがこの事業が誕生した理由です。 学びが人生を豊かにする。それは障害者とその家族にとっても同じです。そこで私たちは、 ライフワイドの視点で障害者とその家族のじりつについて考えてみました。その検討結果が本書で紹介する『青年期のライフワイド学習プログラム』と『親のライフワイド学習プログラム』です。 これらの学びのプログラムが障害者とその家族にとって「じりつ」にむけて楽しんで取り組める学びになることを願っています。 |
||||||||||||
助成機関 |
|||||||||||||
事業成果物種類 |
冊子
|
||||||||||||
事業成果物 |
|